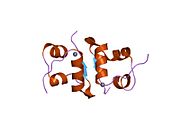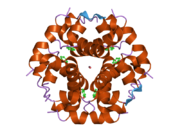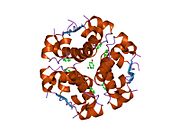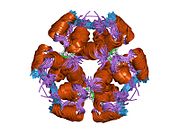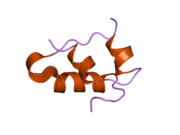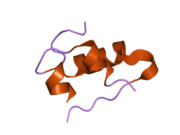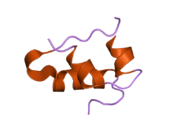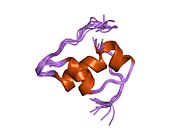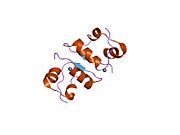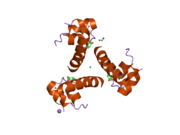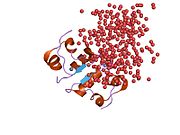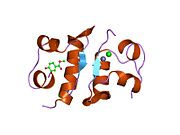Insulin/ja: Difference between revisions
Created page with "第一相放出の説明は以下の通りである: * グルコースはグルコーストランスポーターGLUT 2を介してβ細胞に入る。低血糖レベルではグルコースはほとんどβ細胞に入らないが、高血糖濃度では大量のグルコースがβ細胞に入る。 * β細胞に入ったグルコースはグルコキナーゼ(Hexokinase/ja#Types of mammalia..." Tags: Mobile edit Mobile web edit |
|||
| Line 74: | Line 74: | ||
[[islets of Langerhans/ja|ランゲルハンス島]]の[[Beta Cell/ja|ベータ細胞]]は、2つのフェーズでインスリンを放出する。第一段階の放出は、血糖値の上昇に反応して急速に引き起こされ、約10分間持続する。第二相は、糖とは無関係に引き起こされる新しく形成された小胞の持続的なゆっくりとした放出で、2~3時間でピークに達する。インスリン放出の2つの段階は、インスリン顆粒が多様な発現集団または "プール"に存在することを示唆している。インスリンのエキソサイトーシスの第一段階では、エキソサイトーシスに適した顆粒のほとんどがカルシウムの内在化後に放出される。このプールはRRP(Readily Releasable Pool)として知られている。RRP顆粒は全インスリン含有顆粒集団の0.3-0.7%を占め、細胞膜に隣接して存在する。エキソサイトーシスの第二段階において、インスリン顆粒は細胞膜への顆粒の動員を必要とし、その放出を受けるには事前の準備が必要である。従って、インスリン放出の第二段階は、顆粒が放出の準備をする速度に支配される。このプールはリザーブプール(RP)として知られている。RPはRRPよりも放出速度が遅い(RRP:18顆粒/分、RP:6顆粒/分)。第一相インスリン放出の低下は、[[type 2 diabetes/ja|2型糖尿病]]の発症を予測する最も早期に検出可能なβ細胞の欠陥であるかもしれない。第一相分泌と[[Insulin resistance/ja|インスリン感受性]]は糖尿病の独立した予測因子である。 | [[islets of Langerhans/ja|ランゲルハンス島]]の[[Beta Cell/ja|ベータ細胞]]は、2つのフェーズでインスリンを放出する。第一段階の放出は、血糖値の上昇に反応して急速に引き起こされ、約10分間持続する。第二相は、糖とは無関係に引き起こされる新しく形成された小胞の持続的なゆっくりとした放出で、2~3時間でピークに達する。インスリン放出の2つの段階は、インスリン顆粒が多様な発現集団または "プール"に存在することを示唆している。インスリンのエキソサイトーシスの第一段階では、エキソサイトーシスに適した顆粒のほとんどがカルシウムの内在化後に放出される。このプールはRRP(Readily Releasable Pool)として知られている。RRP顆粒は全インスリン含有顆粒集団の0.3-0.7%を占め、細胞膜に隣接して存在する。エキソサイトーシスの第二段階において、インスリン顆粒は細胞膜への顆粒の動員を必要とし、その放出を受けるには事前の準備が必要である。従って、インスリン放出の第二段階は、顆粒が放出の準備をする速度に支配される。このプールはリザーブプール(RP)として知られている。RPはRRPよりも放出速度が遅い(RRP:18顆粒/分、RP:6顆粒/分)。第一相インスリン放出の低下は、[[type 2 diabetes/ja|2型糖尿病]]の発症を予測する最も早期に検出可能なβ細胞の欠陥であるかもしれない。第一相分泌と[[Insulin resistance/ja|インスリン感受性]]は糖尿病の独立した予測因子である。 | ||
第一相放出の説明は以下の通りである: | |||
* グルコースは[[glucose transporters/ja|グルコーストランスポーター]][[Glucose transporter/ja|GLUT 2]]を介してβ細胞に入る。低血糖レベルではグルコースはほとんどβ細胞に入らないが、高血糖濃度では大量のグルコースがβ細胞に入る。 | |||
* | * β細胞に入ったグルコースは[[glucokinase/ja|グルコキナーゼ]]([[Hexokinase/ja#Types of mammalian hexokinase|ヘキソキナーゼIV]])によって[[glucose-6-phosphate/ja|グルコース-6-リン酸]](G-6-P)にリン酸化される。つまり、細胞内のG-6-P濃度は血糖濃度に比例したままである。 | ||
* | * グルコース-6-リン酸は[[Glycolysis/ja|解糖経路]]に入り、次に[[pyruvate dehydrogenase/ja|ピルビン酸デヒドロゲナーゼ]]反応を経て[[Krebs cycle/ja|クレブスサイクル]]に入り、そこで複数の高エネルギー[[adenosine triphosphate/ja|ATP]]分子が[[acetyl CoA/ja|アセチルCoA]](クレブスサイクルの基質)の酸化によって産生され、細胞内のATP:ADP比の上昇をもたらす。 | ||
* | * 細胞内のATP:ADP比が増加すると、ATP感受性のSUR1/[[Kir6.2/ja|Kir6.2]][[potassium channel/ja|カリウムチャネル]]([[sulfonylurea receptor/ja|スルホニルウレア受容体]]を参照)を閉じる。これにより、カリウムイオン(K<sup>+</sup>)が拡散促進によって細胞外に出ることができなくなり、細胞内にカリウムイオンが蓄積する。その結果、細胞内は外部に対して陰性化し、細胞表面膜の脱分極につながる。 | ||
* | * [[depolarization/ja|脱分極]]すると、電位依存性[[calcium channels/ja|カルシウムイオン(Ca<sup>2+</sup>)チャネル]]が開き、カルシウムイオンが拡散促進によって細胞内に移動する。 | ||
* | * 細胞質カルシウムイオン濃度は、リアノジン受容体の活性化による細胞内貯蔵カルシウムの放出によっても上昇する。 | ||
* | * β細胞の細胞質内のカルシウムイオン濃度は、細胞外の[[ligand/ja|リガンド]](ホルモンまたは神経伝達物質)と[[G protein/ja|Gタンパク質]]共役型膜受容体との結合によって生じる[[phospholipase/ja|ホスホリパーゼC]]の活性化によっても、あるいは追加的に上昇する。ホスホリパーゼCは膜リン脂質である[[phosphatidyl inositol 4,5-bisphosphate/ja|ホスファチジルイノシトール4,5-ビスホスフェート]]を[[inositol 1,4,5-trisphosphate/ja|イノシトール1,4,5-トリスホスフェート]]と[[diglyceride/ja|ジアシルグリセロール]]に切断する。その後、イノシトール1,4,5-三リン酸(IP3)は[[endoplasmic reticulum/ja|小胞体]](ER)の細胞膜にある受容体タンパク質に結合する。これにより、IP3ゲートチャネルを介してERからCa<sup>2+</sup>イオンが放出され、高血糖の影響とは無関係にカルシウムイオンの細胞質濃度が上昇する。膵島への[[Parasympathetic nervous system/ja|副交感神経]]刺激は、この経路を介して作用し、血中へのインスリン分泌を増加させる。 | ||
* | * 細胞質内のカルシウムイオンの量が著しく増加すると、細胞内の[[secretion/ja|分泌]]小胞に蓄えられていた、以前に合成されたインスリンが血液中に放出される。[[vesicle (biology)/ja|小胞]]に貯蔵されていた。 | ||
* | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
Revision as of 15:10, 19 March 2024
| INS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aliases | IDDMIDDM1IDDM2ILPRIRDNMODY10insulinPNDM4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| External IDs | GeneCards: [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wikidata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

インスリン(Insulin、/ˈɪn.sjʊ.lɪn/、ラテン語の島に由来)は、ヒトにおいてインスリン(INS)によってコードされる膵島のβ細胞によって産生されるペプチドホルモンである。遺伝子によってコードされている。体内の主な|アナボリックホルモンと考えられている。血液から肝臓、脂肪、骨格筋細胞へのグルコースの吸収を促進することによって、炭水化物、脂肪、タンパク質の代謝を調節する。 これらの組織において、吸収されたグルコースは糖新生を介してグリコーゲンに変換されるか、または脂肪形成を介して脂肪(トリグリセリド)に変換する際に使用され、肝臓の場合は両方である。肝臓によるグルコースの生産と分泌は、血中の高濃度のインスリンによって強く阻害される。循環インスリンはまた、多種多様な組織におけるタンパク質の合成に影響を与える。したがって、同化ホルモンであり、血中の小分子の細胞内の大分子への変換を促進する。血中のインスリン濃度が低いと、広範な異化、特に予備軍体脂肪の代謝を促進することにより、逆の効果をもたらす。
β細胞は血糖値に敏感で、グルコースレベルが高いとインスリンを血液中に分泌し、グルコースレベルが低いとインスリンの分泌を抑制する。インスリン産生はグルコースによっても調節される:高グルコースではインスリン産生が促進され、低グルコースレベルでは産生が低下する。インスリンは細胞内でのグルコースの取り込みと代謝を促進し、血糖値を下げる。その隣のα細胞は、β細胞からの合図を受けて、血糖値が低いと分泌を増やし、グルコース濃度が高いと分泌を減らすという逆の方法で、血液中にグルカゴンを分泌する。グルカゴンは肝臓での糖新生とグリコーゲン分解を刺激することで血糖値を上昇させる。血中グルコース濃度に応じたインスリンとグルカゴンの血中への分泌は、グルコースホメオスタシスの主要なメカニズムである。
インスリンの活性が低下したり消失したりすると、血糖値が高い状態(高血糖)である糖尿病になる。この病気には2つのタイプがある。1型糖尿病では、自己免疫反応によってβ細胞が破壊され、インスリンが合成されなくなり、血液中に分泌されなくなる。2型糖尿病では、β細胞の破壊は1型ほど顕著ではなく、自己免疫過程によるものではない。その代わりに、膵島にアミロイドが蓄積し、その解剖学的・生理学的構造が破壊されると考えられる。2型糖尿病の発症機序はよくわかっていないが、膵島β細胞の個体数の減少、生存している膵島β細胞の分泌機能の低下、末梢組織のインスリン抵抗性が関与していることが知られている。2型糖尿病は、血糖値の影響を受けず、血糖値にも反応しないグルカゴン分泌の増加を特徴とする。しかし、インスリンは依然として血中グルコースに反応して血中に分泌される。その結果、血液中にグルコースが蓄積する。
ヒトのインスリンタンパク質は51個のアミノ酸から構成され、5808Daの分子量を持つ。A鎖とB鎖がジスルフィド結合で結合したヘテロダイマーである。インスリンの構造は動物の種間でわずかに異なる。ヒト以外の動物由来のインスリンは、これらの変異のため、ヒトのインスリンとは有効性(糖代謝効果)が多少異なる。特に豚のインスリンはヒトのものに近く、ヒトのインスリンが組換えDNA技術によって大量に生産できるようになる前は、1型糖尿病患者の治療に広く用いられていた。
インスリンは最初に発見されたペプチドホルモンである。フレデリック・バンティングとチャールズ・ベストは、トロント大学のジョン・マクラウドの研究室で研究し、1921年に犬の膵臓からインスリンを初めて単離した。フレデリック・サンガーは1951年にアミノ酸構造を決定し、インスリンは完全に配列が決定された最初のタンパク質となった。1969年にドロシー・ホジキンによって固体状態のインスリンの結晶構造が決定された。インスリンはまた、化学的に合成され、DNA組み換え技術によって生産された最初のタンパク質である。基本的な保健システムで必要とされる最も重要な医薬品であるWHO必須医薬品モデルリストに掲載されている。
進化と種の分布
インスリンは10億年以上前に誕生した可能性がある。インスリンの分子的起源は、少なくとも最も単純な単細胞真核生物まで遡る。動物以外では、インスリン様タンパク質は菌類や原生生物にも存在することが知られている。
インスリンは、ほとんどの脊椎動物では膵島のβ細胞によって、一部の硬骨魚ではブロックマン体によって産生される。円錐カタツムリ: コヌス・ジオグラファスとコヌス・チューリパは小魚を狩る毒を持つ巻き貝で、毒のカクテルにインスリンの改良型を使用している。このインスリン毒素は、カタツムリ本来のインスリンよりも魚類のインスリンに近い構造をしており、血糖値を下げることで獲物の魚の動きを鈍らせる。
生産

インスリンは、哺乳類では膵島のβ細胞、一部の魚類ではブロックマン体でのみ産生される。ヒトのインスリンは11番染色体上にあるINS遺伝子から産生される。1つはほとんどの哺乳類遺伝子のホモログ(Ins2)であり、もう1つはプロモーター配列を含むがイントロンを欠くレトロポーズドコピー(Ins1)である。インスリン遺伝子の転写は、血糖値の上昇に反応して増加する。これは主に、遺伝子の転写開始部位の約400塩基対前にあるエンハンサー配列に結合する転写因子によって制御されている。
インスリン分泌に影響を及ぼす主な転写因子は、PDX1、NeuroD1、MafAである。
低グルコース状態では、PDX1(膵・十二指腸ホメオボックスタンパク質1)は、HDAC1および2との相互作用の結果、核周辺に位置し、インスリン分泌のダウンレギュレーションをもたらす。血中グルコース濃度の上昇はPDX1のリン酸化を引き起こし、核内転移してインスリンプロモーター内のA3エレメントに結合する。核内移行したPDX1は、コアクチベーターHAT p300およびSETD7と相互作用する。PDX1は、メチル化だけでなく、アセチル化や脱アセチル化を通してヒストンの修飾に影響を与える。また、グルカゴンを抑制するとも言われている。
β2としても知られるNeuroD1は、エキソサイトーシスに関与する遺伝子の発現を直接誘導することで、膵臓のβ細胞におけるインスリンのエキソサイトーシスを制御している。β2は細胞質に局在しているが、高グルコースに応答するとOGTによって糖鎖化され、ERKによってリン酸化される。核内でβ2はE47とヘテロ二量体化し、インスリンプロモーターのE1エレメントに結合し、β2をアセチル化するコアクチベーターp300をリクルートする。インスリン遺伝子の活性化において、他の転写因子とも相互作用することができる。
MafAは血中グルコース濃度が低いとプロテアソームによって分解される。グルコース濃度が上昇すると、未知のタンパク質がグリコシル化される。このタンパク質は未知の方法でMafAの転写因子として働き、MafAは細胞外に輸送される。そしてMafAは再び核内に移動し、そこでインスリンプロモーターのC1エレメントに結合する。
これらの転写因子は相乗的かつ複雑な配置で働く。血中グルコースの増加は、しばらくするとこれらのタンパク質の結合能を破壊するため、分泌されるインスリンの量を減少させ、糖尿病を引き起こす。結合活性の低下は、グルコースによって誘導される酸化ストレスによって媒介される可能性があり、抗酸化物質は糖毒性膵臓β細胞におけるインスリン分泌の低下を防ぐと言われている。ストレスシグナル分子や活性酸素種は、転写因子を結合する補因子や転写因子そのものを阻害することにより、インスリン遺伝子を阻害する。
ヒトインスリン遺伝子のプロモーター領域にあるいくつかの制御配列は転写因子に結合する。 一般的に、A-boxはPdx1因子に、E-boxはNeuroDに、C-boxはMafAに、cAMP応答エレメントはCREBに結合する。転写を阻害するサイレンサーも存在する。
合成

インスリンは不活性な前駆体分子として合成され、「プレプロインスリン」と呼ばれる110アミノ酸長のタンパク質である。プレプロインスリンは粗面小胞体(RER)に直接翻訳され、そこでシグナルペプチドがシグナルペプチダーゼによって除去され、"プロインスリン "が形成される。プロインスリンが折り畳みされると、「A鎖」と「B鎖」と呼ばれるタンパク質の反対側の末端が3つのジスルフィド結合で融合される。折り畳まれたプロインスリンはゴルジ装置を通過し、特殊な分泌小胞にパッケージされる。顆粒では、プロインスリンはプロテイン転換酵素1/3とプロテイン転換酵素2によって切断され、「C-ペプチド」と呼ばれるタンパク質の中間部分が取り除かれる。最後に、カルボキシペプチダーゼEがタンパク質の末端から2対のアミノ酸を除去し、2つのジスルフィド結合でつながった活性型インスリンA鎖とインスリンB鎖ができる。
その結果、成熟したインスリンは成熟した顆粒内にパッケージされ、代謝シグナル(ロイシン、アルギニン、グルコース、マンノースなど)と迷走神経刺激を待って、細胞から循環中にエキソサイトーズされる。
インスリンとその関連タンパク質は脳内で生成されることが示されており、これらのタンパク質のレベル低下はアルツハイマー病と関連している。
インスリンの分泌は、β2受容体の刺激によっても促進され、α1受容体の刺激では抑制される。さらに、コルチゾール、グルカゴン、成長ホルモンはストレス時にインスリンの作用に拮抗する。インスリンはまた、脂肪組織におけるホルモン感受性リパーゼによる脂肪酸放出を阻害する。
構造

ホルモンは一般的に小さな化学分子であろうという当初の考えに反して、その構造が知られている最初のペプチドホルモンとして、インスリンは非常に大きいことが発見された。ヒトインスリンの単一のタンパク質(モノマー)は、51アミノ酸から構成され、5808Daの分子質量を有する。ヒトインスリンの分子式は、C257H383N65O77S6である。A鎖とB鎖という2本のペプチド鎖(ダイマー)が2つのジスルフィド結合によって結合したものである。A鎖は21個のアミノ酸からなり、B鎖は30個のアミノ酸からなる。連結(鎖間)ジスルフィド結合は、A7-B7位とA20-B19位の間のシステイン残基で形成される。A鎖内にはさらに(鎖内)ジスルフィド結合がA6位とA11位のシステイン残基間に存在する。A鎖は、A1-A8とA12-A19に2つのαヘリカル領域があり、これらは反平行である。一方、B鎖は、ジスルフィド結合に挟まれた中央のαヘリックス(残基B9-B19をカバー)と2つのβシート(B7-B10とB20-B23をカバー)を持つ。
インスリンのアミノ酸配列は強保存であり、種間でわずかに異なるだけである。ウシのインスリンは3つのアミノ酸残基のみ、ポルシンのインスリンは1つのアミノ酸残基のみヒトと異なる。ある種の魚のインスリンでさえ、ヒトに臨床的に有効であるほどヒトに似ている。いくつかの無脊椎動物のインスリンはヒトのインスリンと配列が非常に似ており、同様の生理学的効果を持つ。多様な種のインスリン配列に見られる強い相同性は、動物の進化の歴史の大部分にわたって保存されてきたことを示唆している。しかし、プロインスリンのC-ペプチドは、種によってかなり異なる。
インスリンは6量体(インスリン分子6個の単位)として体内で生成・貯蔵されるが、活性型は単量体である。六量体の大きさは約36000Daである。6つの分子は3つの二量体として結合し、対称的な分子を形成する。重要な特徴は、対称軸上に亜鉛原子(Zn2+)が存在することで、この亜鉛原子は3つの水分子とB10位の3つのヒスチジン残基に囲まれている。
六量体は長期安定性を持つ不活性型であり、反応性の高いインスリンを保護しながらも容易に利用できるようにする役割を果たす。六量体-単量体変換は、注射用インスリン製剤の中心的な側面の一つである。しかし、拡散速度は粒子径に反比例するため、モノマーは反応速度の速い薬物である。即効性のある薬物は、インスリン注射を食事の時間より何時間も前にする必要がないことを意味し、その結果、糖尿病患者の毎日のスケジュールに柔軟性を与える。インスリンは凝集し、線維状のβシートを形成することがある。これは注射アミロイドーシスの原因となり、インスリンの長期保存を妨げる。
機能
分泌
ランゲルハンス島のベータ細胞は、2つのフェーズでインスリンを放出する。第一段階の放出は、血糖値の上昇に反応して急速に引き起こされ、約10分間持続する。第二相は、糖とは無関係に引き起こされる新しく形成された小胞の持続的なゆっくりとした放出で、2~3時間でピークに達する。インスリン放出の2つの段階は、インスリン顆粒が多様な発現集団または "プール"に存在することを示唆している。インスリンのエキソサイトーシスの第一段階では、エキソサイトーシスに適した顆粒のほとんどがカルシウムの内在化後に放出される。このプールはRRP(Readily Releasable Pool)として知られている。RRP顆粒は全インスリン含有顆粒集団の0.3-0.7%を占め、細胞膜に隣接して存在する。エキソサイトーシスの第二段階において、インスリン顆粒は細胞膜への顆粒の動員を必要とし、その放出を受けるには事前の準備が必要である。従って、インスリン放出の第二段階は、顆粒が放出の準備をする速度に支配される。このプールはリザーブプール(RP)として知られている。RPはRRPよりも放出速度が遅い(RRP:18顆粒/分、RP:6顆粒/分)。第一相インスリン放出の低下は、2型糖尿病の発症を予測する最も早期に検出可能なβ細胞の欠陥であるかもしれない。第一相分泌とインスリン感受性は糖尿病の独立した予測因子である。
第一相放出の説明は以下の通りである:
- グルコースはグルコーストランスポーターGLUT 2を介してβ細胞に入る。低血糖レベルではグルコースはほとんどβ細胞に入らないが、高血糖濃度では大量のグルコースがβ細胞に入る。
- β細胞に入ったグルコースはグルコキナーゼ(ヘキソキナーゼIV)によってグルコース-6-リン酸(G-6-P)にリン酸化される。つまり、細胞内のG-6-P濃度は血糖濃度に比例したままである。
- グルコース-6-リン酸は解糖経路に入り、次にピルビン酸デヒドロゲナーゼ反応を経てクレブスサイクルに入り、そこで複数の高エネルギーATP分子がアセチルCoA(クレブスサイクルの基質)の酸化によって産生され、細胞内のATP:ADP比の上昇をもたらす。
- 細胞内のATP:ADP比が増加すると、ATP感受性のSUR1/Kir6.2カリウムチャネル(スルホニルウレア受容体を参照)を閉じる。これにより、カリウムイオン(K+)が拡散促進によって細胞外に出ることができなくなり、細胞内にカリウムイオンが蓄積する。その結果、細胞内は外部に対して陰性化し、細胞表面膜の脱分極につながる。
- 脱分極すると、電位依存性カルシウムイオン(Ca2+)チャネルが開き、カルシウムイオンが拡散促進によって細胞内に移動する。
- 細胞質カルシウムイオン濃度は、リアノジン受容体の活性化による細胞内貯蔵カルシウムの放出によっても上昇する。
- β細胞の細胞質内のカルシウムイオン濃度は、細胞外のリガンド(ホルモンまたは神経伝達物質)とGタンパク質共役型膜受容体との結合によって生じるホスホリパーゼCの活性化によっても、あるいは追加的に上昇する。ホスホリパーゼCは膜リン脂質であるホスファチジルイノシトール4,5-ビスホスフェートをイノシトール1,4,5-トリスホスフェートとジアシルグリセロールに切断する。その後、イノシトール1,4,5-三リン酸(IP3)は小胞体(ER)の細胞膜にある受容体タンパク質に結合する。これにより、IP3ゲートチャネルを介してERからCa2+イオンが放出され、高血糖の影響とは無関係にカルシウムイオンの細胞質濃度が上昇する。膵島への副交感神経刺激は、この経路を介して作用し、血中へのインスリン分泌を増加させる。
- 細胞質内のカルシウムイオンの量が著しく増加すると、細胞内の分泌小胞に蓄えられていた、以前に合成されたインスリンが血液中に放出される。小胞に貯蔵されていた。
This is the primary mechanism for release of insulin. Other substances known to stimulate insulin release include the amino acids arginine and leucine, parasympathetic release of acetylcholine (acting via the phospholipase C pathway), sulfonylurea, cholecystokinin (CCK, also via phospholipase C), and the gastrointestinally derived incretins, such as glucagon-like peptide-1 (GLP-1) and glucose-dependent insulinotropic peptide (GIP).
Release of insulin is strongly inhibited by norepinephrine (noradrenaline), which leads to increased blood glucose levels during stress. It appears that release of catecholamines by the sympathetic nervous system has conflicting influences on insulin release by beta cells, because insulin release is inhibited by α2-adrenergic receptors and stimulated by β2-adrenergic receptors. The net effect of norepinephrine from sympathetic nerves and epinephrine from adrenal glands on insulin release is inhibition due to dominance of the α-adrenergic receptors.
When the glucose level comes down to the usual physiologic value, insulin release from the β-cells slows or stops. If the blood glucose level drops lower than this, especially to dangerously low levels, release of hyperglycemic hormones (most prominently glucagon from islet of Langerhans alpha cells) forces release of glucose into the blood from the liver glycogen stores, supplemented by gluconeogenesis if the glycogen stores become depleted. By increasing blood glucose, the hyperglycemic hormones prevent or correct life-threatening hypoglycemia.
Evidence of impaired first-phase insulin release can be seen in the glucose tolerance test, demonstrated by a substantially elevated blood glucose level at 30 minutes after the ingestion of a glucose load (75 or 100 g of glucose), followed by a slow drop over the next 100 minutes, to remain above 120 mg/100 mL after two hours after the start of the test. In a normal person the blood glucose level is corrected (and may even be slightly over-corrected) by the end of the test. An insulin spike is a 'first response' to blood glucose increase, this response is individual and dose specific although it was always previously assumed to be food type specific only.
Oscillations
Even during digestion, in general, one or two hours following a meal, insulin release from the pancreas is not continuous, but oscillates with a period of 3–6 minutes, changing from generating a blood insulin concentration more than about 800 p mol/l to less than 100 pmol/L (in rats). This is thought to avoid downregulation of insulin receptors in target cells, and to assist the liver in extracting insulin from the blood. This oscillation is important to consider when administering insulin-stimulating medication, since it is the oscillating blood concentration of insulin release, which should, ideally, be achieved, not a constant high concentration. This may be achieved by delivering insulin rhythmically to the portal vein, by light activated delivery, or by islet cell transplantation to the liver.
Blood insulin level

The blood insulin level can be measured in international units, such as µIU/mL or in molar concentration, such as pmol/L, where 1 µIU/mL equals 6.945 pmol/L. A typical blood level between meals is 8–11 μIU/mL (57–79 pmol/L).
Signal transduction
The effects of insulin are initiated by its binding to a receptor, the insulin receptor (IR), present in the cell membrane. The receptor molecule contains an α- and β subunits. Two molecules are joined to form what is known as a homodimer. Insulin binds to the α-subunits of the homodimer, which faces the extracellular side of the cells. The β subunits have tyrosine kinase enzyme activity which is triggered by the insulin binding. This activity provokes the autophosphorylation of the β subunits and subsequently the phosphorylation of proteins inside the cell known as insulin receptor substrates (IRS). The phosphorylation of the IRS activates a signal transduction cascade that leads to the activation of other kinases as well as transcription factors that mediate the intracellular effects of insulin.
The cascade that leads to the insertion of GLUT4 glucose transporters into the cell membranes of muscle and fat cells, and to the synthesis of glycogen in liver and muscle tissue, as well as the conversion of glucose into triglycerides in liver, adipose, and lactating mammary gland tissue, operates via the activation, by IRS-1, of phosphoinositol 3 kinase (PI3K). This enzyme converts a phospholipid in the cell membrane by the name of phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate (PIP2), into phosphatidylinositol 3,4,5-triphosphate (PIP3), which, in turn, activates protein kinase B (PKB). Activated PKB facilitates the fusion of GLUT4 containing endosomes with the cell membrane, resulting in an increase in GLUT4 transporters in the plasma membrane. PKB also phosphorylates glycogen synthase kinase (GSK), thereby inactivating this enzyme. This means that its substrate, glycogen synthase (GS), cannot be phosphorylated, and remains dephosphorylated, and therefore active. The active enzyme, glycogen synthase (GS), catalyzes the rate limiting step in the synthesis of glycogen from glucose. Similar dephosphorylations affect the enzymes controlling the rate of glycolysis leading to the synthesis of fats via malonyl-CoA in the tissues that can generate triglycerides, and also the enzymes that control the rate of gluconeogenesis in the liver. The overall effect of these final enzyme dephosphorylations is that, in the tissues that can carry out these reactions, glycogen and fat synthesis from glucose are stimulated, and glucose production by the liver through glycogenolysis and gluconeogenesis are inhibited. The breakdown of triglycerides by adipose tissue into free fatty acids and glycerol is also inhibited.
After the intracellular signal that resulted from the binding of insulin to its receptor has been produced, termination of signaling is then needed. As mentioned below in the section on degradation, endocytosis and degradation of the receptor bound to insulin is a main mechanism to end signaling. In addition, the signaling pathway is also terminated by dephosphorylation of the tyrosine residues in the various signaling pathways by tyrosine phosphatases. Serine/Threonine kinases are also known to reduce the activity of insulin.
The structure of the insulin–insulin receptor complex has been determined using the techniques of X-ray crystallography.
Physiological effects


The actions of insulin on the global human metabolism level include:
- Increase of cellular intake of certain substances, most prominently glucose in muscle and adipose tissue (about two-thirds of body cells)
- Increase of DNA replication and protein synthesis via control of amino acid uptake
- Modification of the activity of numerous enzymes.
The actions of insulin (indirect and direct) on cells include:
- Stimulates the uptake of glucose – Insulin decreases blood glucose concentration by inducing intake of glucose by the cells. This is possible because Insulin causes the insertion of the GLUT4 transporter in the cell membranes of muscle and fat tissues which allows glucose to enter the cell.
- Increased fat synthesis – insulin forces fat cells to take in blood glucose, which is converted into triglycerides; decrease of insulin causes the reverse.
- Increased esterification of fatty acids – forces adipose tissue to make neutral fats (i.e., triglycerides) from fatty acids; decrease of insulin causes the reverse.
- Decreased lipolysis in – forces reduction in conversion of fat cell lipid stores into blood fatty acids and glycerol; decrease of insulin causes the reverse.
- Induced glycogen synthesis – When glucose levels are high, insulin induces the formation of glycogen by the activation of the hexokinase enzyme, which adds a phosphate group in glucose, thus resulting in a molecule that cannot exit the cell. At the same time, insulin inhibits the enzyme glucose-6-phosphatase, which removes the phosphate group. These two enzymes are key for the formation of glycogen. Also, insulin activates the enzymes phosphofructokinase and glycogen synthase which are responsible for glycogen synthesis.
- Decreased gluconeogenesis and glycogenolysis – decreases production of glucose from noncarbohydrate substrates, primarily in the liver (the vast majority of endogenous insulin arriving at the liver never leaves the liver); decrease of insulin causes glucose production by the liver from assorted substrates.
- Decreased proteolysis – decreasing the breakdown of protein
- Decreased autophagy – decreased level of degradation of damaged organelles. Postprandial levels inhibit autophagy completely.
- Increased amino acid uptake – forces cells to absorb circulating amino acids; decrease of insulin inhibits absorption.
- Arterial muscle tone – forces arterial wall muscle to relax, increasing blood flow, especially in microarteries; decrease of insulin reduces flow by allowing these muscles to contract.
- Increase in the secretion of hydrochloric acid by parietal cells in the stomach.
- Increased potassium uptake – forces cells synthesizing glycogen (a very spongy, "wet" substance, that increases the content of intracellular water, and its accompanying K+ ions) to absorb potassium from the extracellular fluids; lack of insulin inhibits absorption. Insulin's increase in cellular potassium uptake lowers potassium levels in blood plasma. This possibly occurs via insulin-induced translocation of the Na+/K+-ATPase to the surface of skeletal muscle cells.
- Decreased renal sodium excretion.tocytes, insulin binding acutely leads to activation of protein phosphatase 2A (PP2A), which dephosphorylates the bifunctional enzyme fructose bisphosphatase-2 (PFKB1), activating the phosphofructokinase-2 (PFK-2) active site. PFK-2 increases production of fructose 2,6-bisphosphate. Fructose 2,6-bisphosphate allosterically activates PFK-1, which favors glycolysis over gluconeogenesis. Increased glycolysis increases the formation of malonyl-CoA, a molecule that can be shunted into lipogenesis and that allosterically inhibits of carnitine palmitoyltransferase I (CPT1), a mitochondrial enzyme necessary for the translocation of fatty acids into the intermembrane space of the mitochondria for fatty acid metabolism.
Insulin also influences other body functions, such as vascular compliance and cognition. Once insulin enters the human brain, it enhances learning and memory and benefits verbal memory in particular. Enhancing brain insulin signaling by means of intranasal insulin administration also enhances the acute thermoregulatory and glucoregulatory response to food intake, suggesting that central nervous insulin contributes to the co-ordination of a wide variety of homeostatic or regulatory processes in the human body. Insulin also has stimulatory effects on gonadotropin-releasing hormone from the hypothalamus, thus favoring fertility.
Degradation
Once an insulin molecule has docked onto the receptor and effected its action, it may be released back into the extracellular environment, or it may be degraded by the cell. The two primary sites for insulin clearance are the liver and the kidney. It is broken down by the enzyme, protein-disulfide reductase (glutathione), which breaks the disulphide bonds between the A and B chains. The liver clears most insulin during first-pass transit, whereas the kidney clears most of the insulin in systemic circulation. Degradation normally involves endocytosis of the insulin-receptor complex, followed by the action of insulin-degrading enzyme. An insulin molecule produced endogenously by the beta cells is estimated to be degraded within about one hour after its initial release into circulation (insulin half-life ~ 4–6 minutes).
Regulator of endocannabinoid metabolism
Insulin is a major regulator of endocannabinoid (EC) metabolism and insulin treatment has been shown to reduce intracellular ECs, the 2-arachidonoylglycerol (2-AG) and anandamide (AEA), which correspond with insulin-sensitive expression changes in enzymes of EC metabolism. In insulin-resistant adipocytes, patterns of insulin-induced enzyme expression is disturbed in a manner consistent with elevated EC synthesis and reduced EC degradation. Findings suggest that insulin-resistant adipocytes fail to regulate EC metabolism and decrease intracellular EC levels in response to insulin stimulation, whereby obese insulin-resistant individuals exhibit increased concentrations of ECs. This dysregulation contributes to excessive visceral fat accumulation and reduced adiponectin release from abdominal adipose tissue, and further to the onset of several cardiometabolic risk factors that are associated with obesity and type 2 diabetes.
Hypoglycemia
Hypoglycemia, also known as "low blood sugar", is when blood sugar decreases to below normal levels. This may result in a variety of symptoms including clumsiness, trouble talking, confusion, loss of consciousness, seizures or death. A feeling of hunger, sweating, shakiness and weakness may also be present.
The most common cause of hypoglycemia is medications used to treat diabetes such as insulin and sulfonylureas. Risk is greater in diabetics who have eaten less than usual, exercised more than usual or have consumed alcohol. Other causes of hypoglycemia include kidney failure, certain tumors, such as insulinoma, liver disease, hypothyroidism, starvation, inborn error of metabolism, severe infections, reactive hypoglycemia and a number of drugs including alcohol. Low blood sugar may occur in otherwise healthy babies who have not eaten for a few hours.
Diseases and syndromes
There are several conditions in which insulin disturbance is pathologic:
- Diabetes – general term referring to all states characterized by hyperglycemia. It can be of the following types:
- Type 1 diabetes – autoimmune-mediated destruction of insulin-producing β-cells in the pancreas, resulting in absolute insulin deficiency
- Type 2 diabetes – either inadequate insulin production by the β-cells or insulin resistance or both because of reasons not completely understood.
- there is correlation with diet, with sedentary lifestyle, with obesity, with age and with metabolic syndrome. Causality has been demonstrated in multiple model organisms including mice and monkeys; importantly, non-obese people do get Type 2 diabetes due to diet, sedentary lifestyle and unknown risk factors, though it is important to note that this may not be a causal relationship.
- it is likely that there is genetic susceptibility to develop Type 2 diabetes under certain environmental conditions
- Other types of impaired glucose tolerance (see Diabetes)
- Insulinoma – a tumor of beta cells producing excess insulin or reactive hypoglycemia.
- Metabolic syndrome – a poorly understood condition first called syndrome X by Gerald Reaven. It is not clear whether the syndrome has a single, treatable cause, or is the result of body changes leading to type 2 diabetes. It is characterized by elevated blood pressure, dyslipidemia (disturbances in blood cholesterol forms and other blood lipids), and increased waist circumference (at least in populations in much of the developed world). The basic underlying cause may be the insulin resistance that precedes type 2 diabetes, which is a diminished capacity for insulin response in some tissues (e.g., muscle, fat). It is common for morbidities such as essential hypertension, obesity, type 2 diabetes, and cardiovascular disease (CVD) to develop.
- Polycystic ovary syndrome – a complex syndrome in women in the reproductive years where anovulation and androgen excess are commonly displayed as hirsutism. In many cases of PCOS, insulin resistance is present.
Medical uses

Biosynthetic human insulin (insulin human rDNA, INN) for clinical use is manufactured by recombinant DNA technology. Biosynthetic human insulin has increased purity when compared with extractive animal insulin, enhanced purity reducing antibody formation. Researchers have succeeded in introducing the gene for human insulin into plants as another method of producing insulin ("biopharming") in safflower. This technique is anticipated to reduce production costs.
Several analogs of human insulin are available. These insulin analogs are closely related to the human insulin structure, and were developed for specific aspects of glycemic control in terms of fast action (prandial insulins) and long action (basal insulins). The first biosynthetic insulin analog was developed for clinical use at mealtime (prandial insulin), Humalog (insulin lispro), it is more rapidly absorbed after subcutaneous injection than regular insulin, with an effect 15 minutes after injection. Other rapid-acting analogues are NovoRapid and Apidra, with similar profiles. All are rapidly absorbed due to amino acid sequences that will reduce formation of dimers and hexamers (monomeric insulins are more rapidly absorbed). Fast acting insulins do not require the injection-to-meal interval previously recommended for human insulin and animal insulins. The other type is long acting insulin; the first of these was Lantus (insulin glargine). These have a steady effect for an extended period from 18 to 24 hours. Likewise, another protracted insulin analogue (Levemir) is based on a fatty acid acylation approach. A myristic acid molecule is attached to this analogue, which associates the insulin molecule to the abundant serum albumin, which in turn extends the effect and reduces the risk of hypoglycemia. Both protracted analogues need to be taken only once daily, and are used for type 1 diabetics as the basal insulin. A combination of a rapid acting and a protracted insulin is also available, making it more likely for patients to achieve an insulin profile that mimics that of the body's own insulin release. Insulin is also used in many cell lines, such as CHO-s, HEK 293 or Sf9, for the manufacturing of monoclonal antibodies, virus vaccines, and gene therapy products.
Insulin is usually taken as subcutaneous injections by single-use syringes with needles, via an insulin pump, or by repeated-use insulin pens with disposable needles. Inhaled insulin is also available in the U.S. market.
The Dispovan Single-Use Pen Needle by HMD is India’s first insulin pen needle that makes self-administration easy. Featuring extra-thin walls and a multi-bevel tapered point, these pen needles prioritise patient comfort by minimising pain and ensuring seamless medication delivery. The product aims to provide affordable Pen Needles to the developing part of the country through its wide distribution channel. Additionally, the universal design of these needles guarantees compatibility with all insulin pens.
Unlike many medicines, insulin cannot be taken by mouth because, like nearly all other proteins introduced into the gastrointestinal tract, it is reduced to fragments, whereupon all activity is lost. There has been some research into ways to protect insulin from the digestive tract, so that it can be administered orally or sublingually.
In 2021, the World Health Organization added insulin to its model list of essential medicines.
Insulin, and all other medications, are supplied free of charge to people with diabetes by the National Health Service in the countries of the United Kingdom.
History of study
Discovery
In 1869, while studying the structure of the pancreas under a microscope, Paul Langerhans, a medical student in Berlin, identified some previously unnoticed tissue clumps scattered throughout the bulk of the pancreas. The function of the "little heaps of cells", later known as the islets of Langerhans, initially remained unknown, but Édouard Laguesse later suggested they might produce secretions that play a regulatory role in digestion. Paul Langerhans' son, Archibald, also helped to understand this regulatory role.
In 1889, the physician Oskar Minkowski, in collaboration with Joseph von Mering, removed the pancreas from a healthy dog to test its assumed role in digestion. On testing the urine, they found sugar, establishing for the first time a relationship between the pancreas and diabetes. In 1901, another major step was taken by the American physician and scientist Eugene Lindsay Opie, when he isolated the role of the pancreas to the islets of Langerhans: "Diabetes mellitus when the result of a lesion of the pancreas is caused by destruction of the islands of Langerhans and occurs only when these bodies are in part or wholly destroyed".
Over the next two decades researchers made several attempts to isolate the islets' secretions. In 1906 George Ludwig Zuelzer achieved partial success in treating dogs with pancreatic extract, but he was unable to continue his work. Between 1911 and 1912, E.L. Scott at the University of Chicago tried aqueous pancreatic extracts and noted "a slight diminution of glycosuria", but was unable to convince his director of his work's value; it was shut down. Israel Kleiner demonstrated similar effects at Rockefeller University in 1915, but World War I interrupted his work and he did not return to it.
In 1916, Nicolae Paulescu developed an aqueous pancreatic extract which, when injected into a diabetic dog, had a normalizing effect on blood sugar levels. He had to interrupt his experiments because of World War I, and in 1921 he wrote four papers about his work carried out in Bucharest and his tests on a diabetic dog. Later that year, he published "Research on the Role of the Pancreas in Food Assimilation".
The name "insulin" was coined by Edward Albert Sharpey-Schafer in 1916 for a hypothetical molecule produced by pancreatic islets of Langerhans (Latin insula for islet or island) that controls glucose metabolism. Unbeknown to Sharpey-Schafer, Jean de Meyer had introduced the very similar word "insuline" in 1909 for the same molecule.
Extraction and purification
In October 1920, Canadian Frederick Banting concluded that the digestive secretions that Minkowski had originally studied were breaking down the islet secretion, thereby making it impossible to extract successfully. A surgeon by training, Banting knew that blockages of the pancreatic duct would lead most of the pancreas to atrophy, while leaving the islets of Langerhans intact. He reasoned that a relatively pure extract could be made from the islets once most of the rest of the pancreas was gone. He jotted a note to himself: "Ligate pancreatic ducts of dog. Keep dogs alive till acini degenerate leaving Islets. Try to isolate the internal secretion of these + relieve glycosurea[sic]."

In the spring of 1921, Banting traveled to Toronto to explain his idea to John Macleod, Professor of Physiology at the University of Toronto. Macleod was initially skeptical, since Banting had no background in research and was not familiar with the latest literature, but he agreed to provide lab space for Banting to test out his ideas. Macleod also arranged for two undergraduates to be Banting's lab assistants that summer, but Banting required only one lab assistant. Charles Best and Clark Noble flipped a coin; Best won the coin toss and took the first shift. This proved unfortunate for Noble, as Banting kept Best for the entire summer and eventually shared half his Nobel Prize money and credit for the discovery with Best. On 30 July 1921, Banting and Best successfully isolated an extract ("isletin") from the islets of a duct-tied dog and injected it into a diabetic dog, finding that the extract reduced its blood sugar by 40% in 1 hour.
Banting and Best presented their results to Macleod on his return to Toronto in the fall of 1921, but Macleod pointed out flaws with the experimental design, and suggested the experiments be repeated with more dogs and better equipment. He moved Banting and Best into a better laboratory and began paying Banting a salary from his research grants. Several weeks later, the second round of experiments was also a success, and Macleod helped publish their results privately in Toronto that November. Bottlenecked by the time-consuming task of duct-tying dogs and waiting several weeks to extract insulin, Banting hit upon the idea of extracting insulin from the fetal calf pancreas, which had not yet developed digestive glands. By December, they had also succeeded in extracting insulin from the adult cow pancreas. Macleod discontinued all other research in his laboratory to concentrate on the purification of insulin. He invited biochemist James Collip to help with this task, and the team felt ready for a clinical test within a month.

On 11 January 1922, Leonard Thompson, a 14-year-old diabetic who lay dying at the Toronto General Hospital, was given the first injection of insulin. However, the extract was so impure that Thompson had a severe allergic reaction, and further injections were cancelled. Over the next 12 days, Collip worked day and night to improve the ox-pancreas extract. A second dose was injected on 23 January, eliminating the glycosuria that was typical of diabetes without causing any obvious side-effects. The first American patient was Elizabeth Hughes, the daughter of U.S. Secretary of State Charles Evans Hughes. The first patient treated in the U.S. was future woodcut artist James D. Havens; John Ralston Williams imported insulin from Toronto to Rochester, New York, to treat Havens.
Banting and Best never worked well with Collip, regarding him as something of an interloper, and Collip left the project soon after. Over the spring of 1922, Best managed to improve his techniques to the point where large quantities of insulin could be extracted on demand, but the preparation remained impure. The drug firm Eli Lilly and Company had offered assistance not long after the first publications in 1921, and they took Lilly up on the offer in April. In November, Lilly's head chemist, George B. Walden discovered isoelectric precipitation and was able to produce large quantities of highly refined insulin. Shortly thereafter, insulin was offered for sale to the general public.
特許
1922年1月末、インスリンの「共同発見者」4人の間に緊張が高まり、コリップは一時、彼の精製プロセスを個別に特許にすると脅した。そこで、非商業的な公衆衛生機関コノート研究所の所長であるジョン・G・フィッツジェラルドが仲立ちに入った。その結果、1922年1月25日の合意では2つの重要な条件が定められた: 1)共同研究者たちは、コンノートとの最初の共同研究期間中、営利目的の製薬会社との間で特許を取らないことに同意する契約を結ぶこと、2)フィッツジェラルドと4人の共同研究者たちの間で最初に話し合いがなされない限り、研究方針の変更は許されないこと、である。これによって意見の対立を抑え、研究をコンノートの公的使命に結びつけることができた。
当初、マクロードとバンティングは、医療倫理上の理由から、インスリンの製法を特許化することに特に消極的であった。しかし、Eli Lilly and Companyがほのめかしていたように、民間の第三者が研究を乗っ取り独占してしまうのではないか、品質管理の能力がなければ安全な流通を保証することは難しいのではないかという懸念が残った。そのためにエドワード・カルヴィン・ケンドールは貴重な助言を与えた。彼は1914年にメイヨー・クリニックでサイロキシンを単離し,自分とメイヨー兄弟とミネソタ大学との間の取り決めによってその製法を特許化し,その特許を公立大学に譲渡した。4月12日、バンティング、ベスト、コリップ、マクラウド、フィッツジェラルドは連名でトロント大学の学長に手紙を送り、同大学の理事会に特許を譲渡することを目的とした同様の取り決めを提案した。その書簡では、
特許は、他者による特許の持ち出しを防ぐ以外のいかなる目的にも使用されることはないだろうと強調されていた。調製方法の詳細が公表されれば、誰でも自由にエキスを調製することができるが、誰も利益を得る独占権を確保することはできないだろう
トロント大学理事会への譲渡は1923年1月15日に完了し、1ドルという形だけの支払いが行われた。この取り決めは、1923年のThe World's Workで「医療倫理の一歩前進」として祝福された。また、2010年代には、ヘルスケアや薬物の値ごろ感の問題に関して、多くのメディアの注目を集めた。
イーライリリーが製造工程の一部を個別に特許化しようとしていることにさらなる懸念が生じたため、コンノートのアシスタントディレクター兼インスリン部門責任者であるロバート・デフリースは、パテントプール方針を確立した。
構造解析と合成
精製された動物由来のインスリンは、当初、実験や糖尿病患者に利用可能な唯一のタイプのインスリンであった。1926年にジョン・ジェイコブ・アベルが結晶化したものを初めて製造した。タンパク質の性質を示す証拠は、1924年にMichael Somogyi、Edward A. Doisy、Philip A. Shafferによって初めて示された。1935年にハンス・ジェンセンとアール・A・エバンス・ジュニアがアミノ酸のフェニルアラニンとプロリンを単離したときに完全に証明された。
インスリンのアミノ酸構造は1951年にFrederick Sangerによって初めて明らかにされ、最初の合成インスリンは1960年代半ばにピッツバーグ大学のPanayotis KatsoyannisとRWTHアーヘン大学のHelmut Zahnの研究室で同時に生産された。合成結晶ウシインスリンは、1965年に中国の研究者によって達成された。インスリンの完全な3次元構造は、1969年にドロシー・ホジキンの研究室でX線結晶学によって決定された。
ハンス・E・ウェーバーがプレプロインスリンを発見したのは、1974年にカリフォルニア大学ロサンゼルス校で研究員として働いていた時である。1973年から1974年にかけて、ウェーバーはメッセンジャーRNAの単離、精製、翻訳方法の技術を学んだ。インスリンをさらに研究するために、彼はロサンゼルスの食肉処理場から膵臓組織を入手し、その後UCLAで家畜から入手した。彼は膵島細胞から全メッセンジャーRNAを単離し、精製し、それをゼノブス・ラエビスの卵母細胞で翻訳し、抗インスリン抗体を用いて沈殿させた。翻訳された全タンパク質をSDSポリアクリルアミドゲル電気泳動とスクロース勾配で測定したところ、インスリンとプロインスリンに対応するピークが分離された。しかし、ウェーバーが驚いたことに、プロインスリンより大きな分子に対応する3番目のピークが分離された。何回か実験を繰り返した後、彼は一貫してプロインスリンの前にこの大きなピークがあることに注目し、これはプロインスリンの上流にあるより大きな前駆体分子に違いないと判断した。1975年5月、ニューヨークで開催されたアメリカ糖尿病学会で、ウェーバーは自分の研究について口頭発表を行い、そこで初めてこの前駆体分子を「プレプロインスリン」と命名した。この口頭発表の後、ウェーバーは、プロインスリンの特徴付けに貢献した研究者であるドナルド・スタイナーから、彼の論文と発見について議論するために夕食に招待された。 1年後の1976年4月、この分子は、ハンス・ウェーバーの研究と発見を参照しながら、スタイナーによってさらに特徴づけられ、配列が決定された。プレプロインスリンは、転写と翻訳の過程を研究するための重要な分子となった。
1978年、アーサー・リッグスと板倉敬一によって、シティ・オブ・ホープのベックマン研究所で、Genentechのハーバート・ボイヤーとの共同研究により、大腸菌を用いて最初の遺伝子操作による合成「ヒト」インスリンが生産された。Swanson、Boyer、Eli Lilly and Companyによって設立されたGenentechは、1982年にヒューマリンというブランド名で初めて市販された生合成ヒトインスリンを販売した。世界中で使用されているインスリンの大部分は、生合成組換え "ヒト "インスリンまたはその類似体である。最近、カナダの研究者グループによって、簡単に栽培できるベニバナ植物を用いた別の方法が、より安価なインスリンの生産に使われるようになった。
組換えインスリンは酵母(通常サッカロマイセス・セレビシエ)または大腸菌で産生される。酵母では、インスリンはKexIIエンドプロテアーゼ(PCI/PCIIの酵母ホモログ)部位でインスリンA鎖とC末端に切断されたインスリンB鎖を分離した一本鎖タンパク質として操作される。 化学的に合成されたC末端テールは、次に安価なプロテアーゼであるトリプシンを用いた逆プロテオリシスによってインスリンにグラフトされる。通常、C末端テールのリジンはプロテオリシスを防ぐために化学的保護基で保護されている。 モジュラー合成が容易であることと、その領域での修飾が比較的安全であることが、C末端が修飾された一般的なインスリンアナログ(例:リスプロ、アスパルト、グルリジン)の理由である。 Genentech synthesisやBruce Merrifieldによるような完全な化学合成は、主にインスリンB鎖の沈殿との競合により、2つのインスリン鎖の組み換え効率が低いため好ましくない。
ノーベル賞

1923年のノーベル賞委員会は、インスリンの実用的な抽出をトロント大学のチームに託し、フレデリック・バンティングとジョン・マクラウドの2人にノーベル賞を授与した。彼らはインスリンの発見によって1923年にノーベル生理学・医学賞を受賞した。バンティングはベストの名前が挙がっていないことに憤慨し、彼と賞を分かち合い、マクレオドはすぐにジェームズ・コリップと賞を分かち合った。インスリンの特許はトロント大学に1ドルで売却された。
インスリンに関する研究では、他に2つのノーベル賞が授与されている。1955年にインスリンの一次構造を決定したイギリスの分子生物学者フレデリック・サンガーは1958年にノーベル化学賞を受賞した。ロザリン・サスマン・ヤロウはインスリンのラジオイムノアッセイの開発で1977年のノーベル医学賞を受賞した。
いくつかのノーベル賞もインスリンと間接的な関係がある。悪性貧血に対する最初の効果的な治療法の開発で1934年のノーベル賞を共同受賞したジョージ・マイノットは糖尿病を患っていた。ウィリアム・キャッスルは、1921年のインスリンの発見がミノの生還に間に合ったことで、悪性貧血の治療法の発見にもつながったと観察した。ドロシー・ホジキンは、1964年に結晶学の開発でノーベル化学賞を受賞した。この技術は、1969年にインスリンの完全な分子構造を解読するために使用された。
論争

バンティング、ベスト、コリップ、マクロードが発表した研究は、ヒト患者に使用するのに適した精製インスリンエキスの調製を代表するものであった。パウレスクは治療の原理を発見したが、彼の生理食塩水抽出物はヒトに使用することはできなかった。イアン・マーレイはニコライ・パウレスクに対する「歴史的な誤り」を正すために特に積極的に活動した。マレーはスコットランドのグラスゴーにあるアンダーソン医科大学の生理学教授であり、グラスゴーを代表する病院の代謝疾患科の科長であり、英国糖尿病学会の副会長であり、国際糖尿病連合の創設メンバーであった。マレーはこう書いている:
トロントのチームが研究を開始した当時、すでに膵臓の抗糖尿病ホルモンの抽出に成功し、糖尿病犬の高血糖を抑える効果を証明していた著名なルーマニアの科学者であるパウレスクについては、十分な評価がなされていない。
1923年、ノーベル研究所の元所長であるアルネ・ティセリウスは、私信の中で、パウレスクも同様に受賞に値するという個人的な意見を述べた。
さらに読む
- Laws GM, Reaven A (1999). Insulin resistance : the metabolic syndrome X. Totowa, NJ: Humana Press. ISBN 978-0-89603-588-1.
- Leahy JL, Cefalu WT (22 March 2002). Insulin Therapy (1st ed.). New York: Marcel Dekker. ISBN 978-0-8247-0711-8.
- Kumar S, O'Rahilly S (14 January 2005). Insulin Resistance: Insulin Action and Its Disturbances in Disease. Chichester, England: Wiley. ISBN 978-0-470-85008-4.
- Ehrlich A, Schroeder CL (16 June 2000). Medical Terminology for Health Professions (4th ed.). Thomson Delmar Learning. ISBN 978-0-7668-1297-0.
- Draznin B, LeRoith D (September 1994). Molecular Biology of Diabetes: Autoimmunity and Genetics; Insulin Synthesis and Secretion. Totowa, New Jersey: Humana Press. ISBN 978-0-89603-286-6.
- Misbin RI (February 2022). INSULIN - History from an FDA Insider. Washington, DC: Politics and Prose Publishing. ISBN 978-1-62429-391-7. Archived from the original on 29 June 2022. Retrieved 29 June 2022.
- Famous Canadian Physicians: Sir Frederick Banting at Library and Archives Canada
- McKeage K, Goa KL (2001). "Insulin glargine: a review of its therapeutic use as a long-acting agent for the management of type 1 and 2 diabetes mellitus". Drugs. 61 (11): 1599–624. doi:10.2165/00003495-200161110-00007. PMID 11577797. S2CID 46972328.
- Vecchio I, Tornali C, Bragazzi NL, Martini M (2018). "The Discovery of Insulin: An Important Milestone in the History of Medicine". Frontiers in Endocrinology. 9: 613. doi:10.3389/fendo.2018.00613. PMC 6205949. PMID 30405529.
外部リンク
- University of Toronto Libraries Collection: Discovery and Early Development of Insulin, 1920–1925
- CBC Digital Archives – Banting, Best, Macleod, Collip: Chasing a Cure for Diabetes
- Animations of insulin's action in the body at AboutKidsHealth.ca (archived 9 March 2011)
- Overview of all the structural information available in the PDB for UniProt: P01308 (Insulin) at the PDBe-KB.
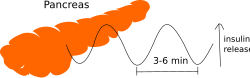
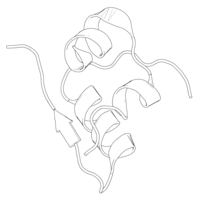











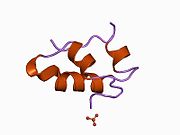

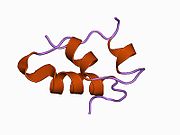


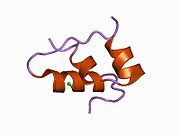
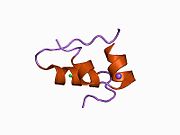
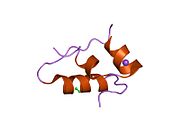








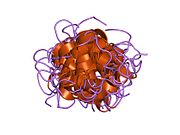




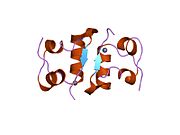
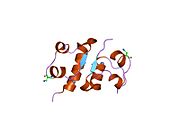

![1jco: Solution structure of the monomeric [Thr(B27)->Pro,Pro(B28)->Thr] insulin mutant (PT insulin)](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9a/PDB_1jco_EBI.jpg/180px-PDB_1jco_EBI.jpg)



![1mhj: SOLUTION STRUCTURE OF THE SUPERACTIVE MONOMERIC DES-[PHE(B25)] HUMAN INSULIN MUTANT. ELUCIDATION OF THE STRUCTURAL BASIS FOR THE MONOMERIZATION OF THE DES-[PHE(B25)] INSULIN AND THE DIMERIZATION OF NATIVE INSULIN](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/PDB_1mhj_EBI.jpg/180px-PDB_1mhj_EBI.jpg)