History of coffee/ja: Difference between revisions
Created page with "近世紀における役割とは対照的に、コーヒーは一部で議論の対象となった。1532年から1533年にかけてファトワーが発効された際、コーヒーとその消費はハラムと定められた。この決定は、アルコールと同様にコーヒーも認知に影響を与えるという考えから来たとみられるが、その影響は異なり、より穏やかなものであった。この規制..." Tags: Mobile edit Mobile web edit |
Created page with "コーヒーの人気が高まるのを抑えようとする試みがなされた。スレイマン1世がまだ権力を握っていた頃、官僚と失業者の両方がコーヒーを消費するのを防ぐ目的で税金が課された。さらなる試みは、1567年のセリム2世と1583年のムラト3世の治世中にも行われた。これは、職人から店主、地元の兵士まで、より控えめな収入の人々がコーヒーを飲み始めた..." |
||
| Line 49: | Line 49: | ||
近世紀における役割とは対照的に、コーヒーは一部で議論の対象となった。1532年から1533年にかけて[[:en:fatwa|ファトワー]]が発効された際、コーヒーとその消費は[[:en:haram|ハラム]]と定められた。この決定は、アルコールと同様にコーヒーも認知に影響を与えるという考えから来たとみられるが、その影響は異なり、より穏やかなものであった。この規制は、オスマン帝国とサファヴィー朝において、タバコやアルコールなどの他の嗜好品の消費を制限しようとする試みとして実施された可能性もある。公共の場所でのコーヒー飲用もまた、蔑視された。公共での消費がタブー視されただけでなく、人々はワインを飲むのと同様の方法で共同のボウルから飲むことが多かった。このことは、コーヒーの飲用様式が再びアルコールと関連付けられたため、コーヒーに対する軽蔑の一因となった可能性が最も高いである。 | 近世紀における役割とは対照的に、コーヒーは一部で議論の対象となった。1532年から1533年にかけて[[:en:fatwa|ファトワー]]が発効された際、コーヒーとその消費は[[:en:haram|ハラム]]と定められた。この決定は、アルコールと同様にコーヒーも認知に影響を与えるという考えから来たとみられるが、その影響は異なり、より穏やかなものであった。この規制は、オスマン帝国とサファヴィー朝において、タバコやアルコールなどの他の嗜好品の消費を制限しようとする試みとして実施された可能性もある。公共の場所でのコーヒー飲用もまた、蔑視された。公共での消費がタブー視されただけでなく、人々はワインを飲むのと同様の方法で共同のボウルから飲むことが多かった。このことは、コーヒーの飲用様式が再びアルコールと関連付けられたため、コーヒーに対する軽蔑の一因となった可能性が最も高いである。 | ||
コーヒーの人気が高まるのを抑えようとする試みがなされた。スレイマン1世がまだ権力を握っていた頃、官僚と失業者の両方がコーヒーを消費するのを防ぐ目的で税金が課された。さらなる試みは、1567年のセリム2世と1583年のムラト3世の治世中にも行われた。これは、職人から店主、地元の兵士まで、より控えめな収入の人々がコーヒーを飲み始めた時であった。コーヒーの飲用を禁じる試みにもかかわらず、コーヒーはアルコールの影響とは比較にならなかったため、ファトワーは最終的に失敗に終わった。コーヒーもアルコールと同様に精神を変える物質と見なされたため、この禁止は物質に対する誤解、あるいは正統派の信仰に基づいて消費を管理しようとする試みであった可能性が高い。この一進一退の状況は、コーヒーが「[[:en:halal|ハラール]]」か「ハラム」かという議論に当てはまる。確かに論争を巻き起こしたが、コーヒーは多くの人々に求められ続けたである。 | |||
<div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | <div lang="en" dir="ltr" class="mw-content-ltr"> | ||
Revision as of 12:49, 2 June 2025


コーヒーの歴史は何世紀にもわたるものであり、その起源はエチオピアに、そして後にイエメンにある。15世紀にはすでにメッカで知られていた。また、15世紀のイエメンのスーフィーのイスラム修道院(ハンカー)では、祈りの際の集中力を高めるためにコーヒーが用いられた。コーヒーは後に16世紀初頭にレバントに広まった。しかし、オスマン帝国やマムルーク朝社会では、それがハラールであるか否かをめぐって一部論争が起きた。コーヒーは16世紀後半に地中海の商業貿易路を通じてイタリアに伝わり、一方、中央ヨーロッパと東ヨーロッパの国々はオスマン帝国からコーヒーを知った。17世紀半ばまでには、インドや東インド諸島にまで到達していたである。

コーヒーハウスは、17世紀後半までに西ヨーロッパ、特にオランダ、イングランド、ドイツで設立された。新世界におけるコーヒーの最も初期の栽培の一つは、1720年にガブリエル・ド・クリューがマルティニークにコーヒーの苗木をもたらした時であった。これらの豆は後に18,680本のコーヒーの木に成長し、サン=ドマングなどの他のカリブ海の島々やメキシコへの普及を可能にした。1788年までに、サン=ドマングは世界のコーヒーの半分を供給したである。
1852年までにブラジルは世界最大のコーヒー生産国となり、それ以来その地位を維持している。1950年以降、コロンビア、コートジボワール、エチオピア、ベトナムなど、いくつかの主要な生産国が出現した。特にベトナムは1999年にコロンビアを抜き、第2位の生産国となったである。
今日、コーヒーは世界で最も人気のある飲料の一つであり、世界的に大きな文化的・経済的影響を与えているである。
語源
コーヒーという言葉は、1582年にオランダ語のkoffieを介して英語に入った。これはオスマン・トルコ語の「kahve (قهوه)」から借用され、さらにこれはアラビア語の「qahwah (قَهْوَة)」から借用されたものである。中世のアラビア語辞書編纂者たちは伝統的に、「qahwah」の語源は、その独特の濃い色から「ワイン」を意味するとし、動詞「qahiya (قَهِيَ)」、すなわち「食欲がない」に由来するとした。しかし、「qahwah」という言葉は、飲み物や豆を指して「暗い」という意味であった可能性が最も高い。セム語派には「qhh」という語根があり、「濃い色」を意味し、それがこの飲み物の自然な呼称となった。この言葉がカッファ県(コーヒーの起源であるアビシニアの一部)というエチオピアの州にちなんで名付けられたという証拠はなく、またその反対を主張する有力な根拠もないし、アラビア語の「quwwa」(「power」)に由来するという証拠もない。 「コーヒー」を意味する別の言葉で、エチオピアの言語で広く使われているものに、buna、bun、būn、またはbuni(言語による)がある。この語群は、アラビア語の「bunn (بن)」、特にコーヒー豆を意味する言葉に由来するとされることが多いが、クシ語派に固有の起源がある可能性も提案されている。
オスマン帝国がコーヒー貿易において優位な地位にあったことは、他のいくつかのヨーロッパ言語にも影響を与えたと考えられており、イタリア語の「caffè」やフランス語の「cafécafé」の語源となった。これらの用語は、オランダ語の「koffie」とほぼ同時期に出現し、ヨーロッパ全体へのコーヒーの新たな広がりを反映している。
「コーヒーポット」と「コーヒーブレイク」という言葉は、それぞれ1705年と1952年に生まれたものである。
遺伝学
アラビカ種の品種に関する遺伝的多様性の研究が行われてきた。これらの研究では、多様性は低いものの、祖先系統から残存するいくつかの異型接合性が保持されていることが判明しており、また近縁の二倍体種であるロブスタ種やリベリカ種との関連も示されている。しかし、アフリカのどこでコーヒーが栽培されていたか、あるいは17世紀以前に現地の人々の誰が刺激物としてコーヒーを使用していたか、あるいはその存在を知っていたかを示す直接的な証拠はこれまで見つかっていない。原種の栽培コーヒーはハラルに由来するとされ、その在来個体群はエチオピアに起源を持ち、スーダンとケニアに近縁の異なる個体群が存在すると考えられている。
歴史



文学的なコーヒー商人フィリップ・シルヴェストル・デュフールが記したコーヒーに関する最も初期の記述は、10世紀のペルシア人医師ムハンマド・イブン・ザカリヤ・アル=ラージー(西洋ではラゼスとして知られる)の著作における「bunchum」への言及である。焙煎したコーヒー豆から飲み物を調製するコーヒーの木と調製に関するより明確な情報は、15世紀後半に遡る。スーフィーのイマーム、ムハンマド・イブン・サイード・アル=ダバニがエチオピアからイエメンへ商品を輸入したことで知られている。コーヒーは、ベルベラとゼイラのソマリ人商人がハラルやアビシニア内陸部から調達したものを、エチオピアからイエメンへ初めて輸出した。アデンの植民地行政官であったヘインズ大尉(1839年-1854年)によると、モカは歴史的に、19世紀にイギリスが支配するアデンがモカのコーヒー貿易を掌握するまで、コーヒーの最大3分の2をベルベラを拠点とする商人から輸入していた。その後、エチオピアのコーヒーの多くはベルベラ経由でアデンに輸出されたである。
ベルベラはアデンに非常に大量の有角牛と羊を供給するだけでなく、アフリカとアデンの間の貿易は毎年着実に大きく増加している。コーヒーだけでも相当量の輸出があり、現在ボンベイ市場では「ベルベラ」コーヒーがモカよりも優位に立っている。ベルベラで積み出されるコーヒーは、はるか内陸のフルラル、アビシニア、カッファから来る。貿易がすべてアデンに一つの港を通じて行われることは、すべての人にとって有利であり、ベルベラはそこにある海岸で、船が穏やかな水域に停泊できる唯一の保護された港である。
コーヒーに関する初期の最も重要な著述家の一人が、1587年にコーヒーの歴史と法的な論争をたどる著作『Umdat al Safwa fi hill al-qahwa(عمدة الصفوة في حل القهوة)』を編纂したアブド・アル=カーディル・アル=ジャズィーリーである。この著作は、コーヒーが「幸福のアラビア」(現在のイエメン)から北方のメッカやメディナ、そしてさらに大きな都市であるカイロ、ダマスカス、バグダッド、コンスタンティノープルへと広まった経緯をたどっている。彼は、アデンのムフティであるシャイフ、ジャマール・アッディーン・アル=ダバーニ(1470年没)が、最初にコーヒーの使用を採用した(およそ1454年)と報告している。
彼はその効能の中に、疲労や倦怠感を払い、体に一定の活気と活力をもたらすことを見出した。
アル=ジャズィーリーの写本は、ヨーロッパにおけるコーヒーの歴史に関しても非常に興味深い。その写本の一部はフランス王立図書館に所蔵され、アントワーヌ・ガランによって『De l'origine et du progrès du café』(1699年)として部分的に翻訳されたである。
中東
イエメンのスーフィーたちは、この飲み物を集中力の助けとして、また神の名を唱える際の精神的な陶酔の一種として利用した。スーフィーたちは夜間の礼拝中に覚醒状態を保つためにそれを用いた。1414年までにこの植物はメッカで知られるようになり、1500年代初頭にはイエメンのモカ港からエジプトと北アフリカのマムルーク朝へと広まった。スーフィズムに関連して、アズハル大学周辺のカイロ(エジプト)には無数のコーヒーハウスが出現した。これらのコーヒーハウスはシリア、特に国際都市アレッポにも開設され、その後1554年にはオスマン帝国の首都コンスタンティノープルにも広がった。コーヒーは1573年にドイツ人医師植物学者レオンハルト・ラウヴォルフによって「chaube」としてアレッポで言及されており、これはコーヒーについて言及した最初のヨーロッパ人である。ラウヴォルフの記述に続いて、他のヨーロッパ人旅行者による記述が続いた。
1511年、メッカの神学法廷で保守的な正統派イマームによって、その覚醒作用を理由に禁止された。しかし、これらの禁止令は1524年にオスマン・トルコのスルタンスレイマン1世の命令によって覆され、大ムフティメフメト・エブスースード・エル=イマーディがコーヒーの摂取を許可するファトワーを発令した。カイロでは1532年に同様の禁止令が敷かれ、コーヒーハウスとコーヒー豆を貯蔵する倉庫が略奪された。16世紀の間には、すでに中東の他の地域、サファヴィー朝、そしてオスマン帝国にまで到達していた。中東からコーヒーを飲む習慣はイタリア、そしてヨーロッパの他の地域へと広がり、コーヒーの木はオランダ人によって東インドとアメリカ大陸に運ばれたである。
エチオピアにおけるコーヒーの規制
コーヒーは18世紀以前のある時期にエチオピア正教会によって禁止された。しかし、19世紀後半になると、エチオピア人のコーヒー飲用に対する態度が軟化し、1880年から1886年の間にその消費が急速に広まった。リチャード・パンクハーストによると、「これは主に、自らもコーヒーを飲んだ皇帝メネリク2世と、コーヒーがムスリムの飲み物であるという聖職者の信仰を払拭するために多大な貢献をしたアブナマテウォスの功績によるものであった。」
イスラムにおけるコーヒー
初期のイスラム医学と科学の実践者たちは、コーヒーの効果がハシシやアルコールのようなものであるという考えに反論し、代わりにアルコールやハシシの誘惑から身を守りながら精神を刺激するこの飲み物の利点を主張した。メッカ、イエメン、カイロのコーヒーハウスは爆発的な人気を博し始め、やがてイスラム帝国の広大な都市における公共生活の中心となる。コーヒーハウスは時に、イスラムの生活、芸術、思想の中心であったバイト・アル=ヒクマやマドラサのように機能した。フォルジャー・シェイクスピア図書館のネハ・ヴェラミは、「これらのコーヒーハウスの歴史は、公共圏の出現、近世イスラム帝国の政治生活へのより広範な人々の参加、そして西洋の傍観者による『東洋』社会への専制政治の疑惑の空虚さという、3つの関連する洞察を提供する」と述べている。コーヒーは、その後数世紀にわたってイスラム文化に深く根付いたのである。
近世紀における役割とは対照的に、コーヒーは一部で議論の対象となった。1532年から1533年にかけてファトワーが発効された際、コーヒーとその消費はハラムと定められた。この決定は、アルコールと同様にコーヒーも認知に影響を与えるという考えから来たとみられるが、その影響は異なり、より穏やかなものであった。この規制は、オスマン帝国とサファヴィー朝において、タバコやアルコールなどの他の嗜好品の消費を制限しようとする試みとして実施された可能性もある。公共の場所でのコーヒー飲用もまた、蔑視された。公共での消費がタブー視されただけでなく、人々はワインを飲むのと同様の方法で共同のボウルから飲むことが多かった。このことは、コーヒーの飲用様式が再びアルコールと関連付けられたため、コーヒーに対する軽蔑の一因となった可能性が最も高いである。
コーヒーの人気が高まるのを抑えようとする試みがなされた。スレイマン1世がまだ権力を握っていた頃、官僚と失業者の両方がコーヒーを消費するのを防ぐ目的で税金が課された。さらなる試みは、1567年のセリム2世と1583年のムラト3世の治世中にも行われた。これは、職人から店主、地元の兵士まで、より控えめな収入の人々がコーヒーを飲み始めた時であった。コーヒーの飲用を禁じる試みにもかかわらず、コーヒーはアルコールの影響とは比較にならなかったため、ファトワーは最終的に失敗に終わった。コーヒーもアルコールと同様に精神を変える物質と見なされたため、この禁止は物質に対する誤解、あるいは正統派の信仰に基づいて消費を管理しようとする試みであった可能性が高い。この一進一退の状況は、コーヒーが「ハラール」か「ハラム」かという議論に当てはまる。確かに論争を巻き起こしたが、コーヒーは多くの人々に求められ続けたである。
Within the Ottoman Empire, shops known as taḥmīskhāne in Ottoman Turkish were used to create coffee using the traditional method of roasting and crushing coffee beans in mortars. Coffee houses located in areas such as Mecca were visited by those from all over: Muslims from mosques, those coming from afar to trade and sell, or simple travelers making their way through.
Despite the controversy over coffee, it was one of the keys to the economy around the Red Sea from the mid-15th century to the mid-17th century. In the past, the Oromo tribe in Ethiopia created foods from coffee plants such as bunna qela, made of butter, salt, and roasted beans. Such a concoction would be used as a basis and altered over time. A more modern beverage known as qishr in Arabic is made of recycled dried cherry skins that would have normally been discarded after being used to create the beverage buna. These cherry skins would then be used to brew a sort of fruit tea. Qishr or cascara in Spanish is sold by coffee farmers even today.
Legendary accounts
There are several legendary accounts of the origin of the consumption of coffee. According to one legend, ancestors of today's Kafficho people in the Kingdom of Kaffa were the first to recognize the energizing effect of the coffee plant. One account involves a 9th-century Ethiopian goatherder, Kaldi, who, noticing the energizing effects when his flock nibbled on the bright red berries of a certain bush, chewed on the fruit himself. His exhilaration prompted him to bring the berries to a monk in a nearby monastery. But the monk disapproved of their use and threw them into the fire, from which an enticing aroma billowed, causing other monks to come and investigate. The roasted beans were quickly raked from the embers, ground up, and dissolved in hot water, yielding the world's first cup of coffee. Since this story is not known to have appeared in writing before Rome-based Maronite Faustus Nairon's De Saluberrima potione Cahue seu Cafe nuncupata Discurscus in 1671, 800 years after it was supposed to have taken place, it is highly likely to be apocryphal.
Another account involves the 13th century Moroccan Sufi mystic Ghothul Akbar Nooruddin Abu al-Hasan al-Shadhili. When traveling in Ethiopia, the legend goes, he observed birds of unusual vitality feeding on berries, and, upon trying the berries, experienced the same vitality. Yet another attributes the discovery of coffee to Sheikh Abu al-Hasan ash-Shadhili's disciple, Omar. According to the ancient chronicle (preserved in the Abd-Al-Kadir manuscript), Omar, who was known for his ability to cure the sick through prayer, was once banished from Mecca to a desert cave near the Ousab City. Starving, Omar chewed berries from nearby shrubbery, but found them to be too bitter. He tried roasting the beans to improve the flavor, but they became too hard. He then tried boiling them to soften the bean, which resulted in a fragrant brown liquid. After drinking the liquid, Omar was revived and survived for days. As stories of this "miracle drug" reached Mecca, Omar was asked to return and was eventually made a saint.
Nepenthe /nɪˈpɛnθi/ (Ancient Greek: νηπενθές, nēpenthés) is possibly derived from a misunderstanding of coffee in the Homeric cycle. It is mentioned as originating in Egypt. The word nepenthe first appears in the fourth book of Homer's Odyssey:
ἔνθ᾽ αὖτ᾽ ἄλλ᾽ ἐνόησ᾽ Ἑλένη Διὸς ἐκγεγαυῖα: |
|
| —Odyssey, Book 4, v. 219–221 |
Figuratively, nepenthe means "that which chases away sorrow". Literally it means 'not-sorrow' or 'anti-sorrow': νη-, nē-, i.e. "not" (privative prefix), and πενθές, from πένθος, pénthos, i.e. "grief, sorrow, or mourning".
In the Odyssey, νηπενθές φάρμακον : nēpenthés phármakon (i.e. an anti-sorrow drug) is a magical potion given to Helen by Polydamna, the wife of the noble Egyptian Thon,
It [coffee] became associated with Muhammad's birthday. Indeed, various legends ascribed coffee's origins to Muhammad, who, through the archangel Gabriel, brought it to man to replace the wine which Islam forbade.
Europe

Coffee was first introduced to Europe in Hungary when the Turks invaded Hungary at the Battle of Mohács in 1526. Within a year, coffee had reached Vienna by the same Turks who fought the Europeans at the Siege of Vienna (1529). Later in the 16th century, coffee was introduced on the island of Malta through slavery. Turkish Muslim slaves had been imprisoned by the Knights of St John in 1565—the year of the Great Siege of Malta, and they used them to make their traditional beverage. Domenico Magri mentioned in his work Virtu del Kafé, "Turks, most skillful makers of this concoction." Also, the German traveler Gustav Sommerfeldt in 1663 wrote "the ability and industriousness with which the Turkish prisoners earn some money, especially by preparing coffee, a powder resembling snuff tobacco, with water and sugar." Coffee was a popular beverage in Maltese high society—many coffee shops opened.
The first mention of coffee in a European text is in Charles de l'Ecluse's Aromatum et simplicium aliquot medica-mentorum apud Indos nascientum historia from 1575. He learnt of coffee from Alphoncius Pansius in Padua. Englishmen passing through Safavid and the Ottoman Empire in the late 16th century noted that coffee was "very good to help digestion, to quicken the spirits, and to cleanse the blood.”
The vibrant trade between the Republic of Venice and the people of North Africa, Egypt, and the East brought a large variety of African goods, including coffee, to this leading European port. Venetian merchants introduced coffee-drinking to the wealthy in Venice, charging them heavily for the beverage. In this way, coffee was introduced to the mainland of Europe. In 1591 Venetian botanist-physician Prospero Alpini became the first to publish a description of the coffee plant in Europe. The first European coffee house apart from those in the Ottoman Empire and in Malta was opened in Venice in 1645.
The first route of travel for coffee was through the massive, sprawling Ottoman Empire that allowed transportation of goods such as coffee to make their way well into Europe, and the second route of travel was from the port of Mocha in Yemen, where the East India Trading Co. bought coffee in masses and transported it back to mainland Europe. Coffee became a crucial part of the culture in most of Europe, with queens, kings, and the general public all becoming extensively enthralled with the product. Rather it be through the term 'coffee arabica' or the transportation of the drink, the passage of coffee into the Western world greatly resembles that of the scientific knowledge and discoveries passed on by the Islamicate Empires.
Austria

The first coffeehouse in Austria opened in Vienna in 1683 after the Battle of Vienna, by using supplies from the spoils obtained after defeating the Turks. The officer who received the coffee beans, Jerzy Franciszek Kulczycki (Georg Franz Kolschitzky), a Polish military officer, opened a coffee house and helped popularize the custom of adding sugar and milk to the coffee. Melange is the typical Viennese coffee, which comes mixed with hot foamed milk, and is usually served with a glass of water.
A distinct Viennese coffee house culture developed in Vienna in the 19th century and then spread throughout Central Europe. Scientists, artists, intellectuals, bon vivants and their financiers met in this special microcosm of the Viennese coffee houses of the Habsburg Empire. World-famous personalities such as Gustav Klimt, Sigmund Freud, James Joyce and Egon Schiele were inspired in the Viennese coffee house. In this diverse coffee house culture of the multicultural Habsburg Empire, different types of coffee preparation also developed. This is how the world-famous cappuccino from the Viennese Kapuziner coffee developed over the Italian-speaking parts of the northern Italian empire.
The first coffeehouse in England was opened in Oxford in 1650. The first coffeehouse in London opened in St. Michael's Alley in Cornhill, London. The proprietor was Pasqua Rosée, the servant of Daniel Edwards, a trader in Turkish goods. Edwards imported the coffee and assisted Rosée in setting up the establishment. Coffee was also brought in through the British East India Company and the Dutch East India Company in the 17th century. Oxford's Queen's Lane Coffee House, established in 1654, is still in existence today. By 1675, there were more than 3,000 coffeehouses throughout England, but there were many disruptions in the progressive movement of coffeehouses between the 1660s and 1670s. During the enlightenment, these early English coffee houses became gathering places used for deep religious and political discussions among the populace, since it was a rare opportunity for sober discussion. This practice became so common, and potentially subversive, that Charles II made an attempt to crush coffee houses in 1670s.
The banning of women from coffeehouses was not universal, for example, women frequented them in Germany, but it appears to have been commonplace elsewhere in Europe, including in England.
Many in this period believed coffee to have medicinal properties. Renowned and eminent physicians often recommended coffee for medicinal purposes and some prescribed it as a cure for nervous disorders. A 1661 tract entitled "A character of coffee and coffee-houses", written by one "M.P.", lists some of these perceived benefits:
'Tis extolled for drying up the Crudities of the Stomack, and for expelling Fumes out of the Head. Excellent Berry! which can cleanse the English-man's Stomak of Flegm, and expel Giddinesse out of his Head.
This new commodity proved controversial among some subjects, however. For instance, the anonymous 1674 "Women's Petition Against Coffee" declared:
the Excessive Use of that Newfangled, Abominable, Heathenish Liquor called COFFEE ...has...Eunucht our Husbands, and Crippled our more kind Gallants, that they are become as Impotent, as Age.
France
Antoine Galland (1646–1715) in his aforementioned translation described the Muslim association with coffee, tea and chocolate: "We are indebted to these great [Arab] physicians for introducing coffee to the modern world through their writings, as well as sugar, tea, and chocolate." Regarding this last, he was quite mistaken however, as chocolate had been brought to Europe from the Americas by the Spanish. Galland reported that he was informed by Mr. de la Croix, the interpreter of King Louis XIV of France, that coffee was brought to Paris by a certain Mr. Thevenot, who had travelled through the East. On his return to that city in 1657, Thevenot gave some of the beans to his friends, one of whom was de la Croix.
In 1669, Soleiman Agha, Ambassador from Sultan Mehmed IV, arrived in Paris with his entourage bringing with him a large quantity of coffee beans. Not only did they provide their French and European guests with coffee to drink, but they also donated some beans to the royal court. Between July 1669 and May 1670, the Ambassador managed to firmly establish the custom of drinking coffee among Parisians.
Germany
In Germany, coffeehouses were first established in North Sea ports, including Wuppertal-Ronsdorf (1673) and Hamburg (1677). Initially, this new beverage was written in the English form coffee, but during the 1700s the Germans gradually adopted the French word café, then slowly changed the spelling to Kaffee, which is the present word. In the 18th century the popularity of coffee gradually spread around the German lands and was taken up by the ruling classes. Coffee was served at the court of the Great Elector, Frederick William of Brandenburg, as early as 1675, but Berlin's first public coffee house did not open until 1721.

Composer Johann Sebastian Bach, who was cantor of St. Thomas Church in Leipzig, in 1723–1750, conducted a musical ensemble at the local Café Zimmermann. Sometime in 1732–1735 he composed the secular "Coffee Cantata" Schweigt stille, plaudert nicht (BWV 211), in which a young woman, Lieschen, pleads with her disapproving father to accept her devotion to drinking coffee, then a newfangled fashion. The libretto includes such lines as:
Ei! wie schmeckt der Coffee süße,
Lieblicher als tausend Küsse,
Milder als Muskatenwein.
Coffee, Coffee muss ich haben,
Und wenn jemand mich will laben,
Ach, so schenkt mir Coffee ein!
(Oh! How sweet coffee does taste,
Better than a thousand kisses,
Milder than muscat wine.
Coffee, coffee, I've got to have it,
And if someone wants to perk me up, *
Oh, just give me a cup of coffee!)
Italy

In Italy, like in most of Europe, coffee arrived in the second half of the 16th century through the commercial routes of the Mediterranean Sea. In 1580 the Venetian botanist and physician Prospero Alpini imported coffee into the Republic of Venice from Egypt, and soon coffee shops started opening one by one when coffee spread and became the drink of the intellectuals, of social gatherings, even of lovers as plates of chocolate and coffee were considered a romantic gift. By the year 1763 Venice alone accounted for more than 200 coffee shops, and the health benefits of the miraculous drink were celebrated by many. Some representatives of the Catholic Church opposed coffee at its first introduction in Italy, believing it to be the "Devil's drink", but Pope Clement VIII, after trying the aromatic drink himself, gave it his blessing, thus boosting further its commercial success and diffusion. Upon tasting coffee, Pope Clement VIII declared: "Why, this Satan's drink is so delicious that it would be a pity to let the infidels have exclusive use of it." Clement allegedly blessed the bean because it appeared better for the people than alcoholic beverages. The year often cited is 1600. It is not clear whether this is a true story, but it may have been found amusing at the time.
In Turin, in 1933, Italian engineer Luigi Di Ponti invented the first moka pot and subsequently sold the patent to Alfonso Bialetti. In 1946 Alfonso's son Renato started industrial production, selling millions of moka pots in one year, versus only 70000 sold by his father in the previous 10, making the coffee maker (as well as coffee) an icon of Italy in the world. Naples, albeit being known today as the city of coffee, has seen it later, probably through the ships coming in the ports of Sicily and Naples itself. Some date the Neapolitan discovery of coffee back to 1614, when the composer, explorer and musicologist Pietro Della Valle sent news from the Holy Land, in his letters to the dear friend, physician, poet, Greek scholar and Mario Schipano and his gathering of intellectuals, of a drink (called kahve) the Arab Muslims brewed in hot pots.
Some believe coffee arrived in Naples earlier, from Salerno and its Schola Medica Salernitana, where the plant came to be used for its medicinal properties between the 14th and 15th centuries. Celebrated by Neapolitan art, literature, music and daily social life, coffee soon became a protagonist in Naples, where it was prepared with great care in the "cuccumella", the typical Neapolitan filter coffee pot derived by the invention of the parisian Morize in 1819. Neapolitan artisans came in touch with it when brought, once again through the sea commercial routes, to the Port of Naples. An indication of the approach of Neapolitans to coffee as a social drink, is the practice of the suspended coffee (the act of paying in advance for a coffee to be consumed by the next customer) invented there and defined by the Neapolitan philosopher and writer Luciano De Crescenzo a coffee "given by an individual to mankind".
Netherlands
The race among Europeans to obtain live coffee trees or beans was eventually won by the Dutch in 1616. Pieter van den Broecke, a Dutch merchant, obtained some of the closely guarded coffee bushes from Mocha, Yemen, in 1616. He took them back to Amsterdam and found a home for them in the Botanical gardens, where they began to thrive. This apparently minor event received little publicity but was to have a major impact on the history of coffee.
The beans that van der Broecke acquired from Mocha forty years earlier adjusted well to conditions in the greenhouses at the Amsterdam Botanical Garden and produced numerous healthy Coffea arabica bushes. In 1658 the Dutch first used them to begin coffee cultivation in Ceylon (now Sri Lanka) and later in southern India. They abandoned this cultivation to focus on their Javanese plantations in order to avoid lowering the price by oversupply.
Within a few years, the Dutch colonies (Java in Asia, Suriname in the Americas) had become the main suppliers of coffee to Europe.
Poland
Coffee reached the Polish–Lithuanian Commonwealth in the 17th century, primarily through merchants trading with the neighbouring Ottoman Empire. The first coffee shops opened a century later. The intake of coffee has grown since the change of government in 1989, though consumption per capita is lower than in most European countries. During the Communist period, where there were shortages of everything, including coffee, Poles developed their own substitute to coffee, Inka, made from roasted cereal. Nowadays, Poland is experiencing an explosion of coffee consumption through rapid expansion of cafes, and new trends such as the specialty coffee.
Americas
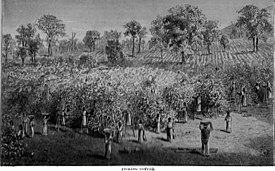
Gabriel de Clieu brought coffee seedlings to Martinique in the Caribbean in 1720. Those sprouts flourished and 50 years later there were 18,680 coffee trees in Martinique enabling the spread of coffee cultivation to Saint-Domingue (Haiti), Mexico and other islands of the Caribbean. The French territory of Saint-Domingue saw coffee cultivated starting in 1734, and by 1788 supplied half the world's coffee. Coffee had a major influence on the geography of Latin America. The French colonial plantations relied heavily on African slave laborers. However, the dreadful conditions that the slaves worked in on coffee plantations were a factor in the soon-to-follow Haitian Revolution. The coffee industry never fully recovered there.
Coffee also found its way to the Isle of Bourbon, now known as Réunion, in the Indian Ocean. The plant produced smaller beans and was deemed a different variety of arabica known as var. Bourbon. The Santos coffee of Brazil and the Oaxaca coffee of Mexico are the progeny of that Bourbon tree. Circa 1727, the King of Portugal sent Francisco de Melo Palheta to French Guiana to obtain coffee seeds to become a part of the coffee market. Francisco initially had difficulty obtaining these seeds, but he captivated the French Governor's wife, and she sent him enough seeds and shoots to commence the coffee industry of Brazil. However, cultivation did not gather momentum until independence in 1822, leading to the clearing of massive tracts of the Atlantic Forest, first from the vicinity of Rio and later São Paulo for coffee plantations. In 1893, the coffee from Brazil was introduced into Kenya and Tanzania (Tanganyika), not far from its place of origin in Ethiopia, 600 years prior, ending its transcontinental journey.
After the Boston Tea Party of 1773, large numbers of Americans switched to drinking coffee during the American Revolution because drinking tea had become unpatriotic.
Cultivation was taken up by many countries in the latter half of the 19th century, and in almost all of them it involved the large-scale displacement and exploitation of indigenous people. Harsh conditions led to many uprisings, coups and bloody suppressions of peasants. For example, Guatemala started producing coffee in the 1500s but lacked the manpower to harvest the coffee beans. As a result, the Guatemalan government forced indigenous people to work on the fields. This led to a strain in the indigenous and Guatemalan people's relationship that still exists today. A notable exception is Costa Rica where a lack of ready labor prevented the formation of large farms. Smaller farms and more egalitarian conditions ameliorated unrest over the 19th and 20th centuries.
In the 20th century Latin American countries faced a possible economic collapse. Before World War II Europe was consuming large amounts of coffee. Once the war started Latin America lost 40% of its market and was on the verge of economic collapse. Coffee was and is a Latin American commodity. The United States saw this and talked with the Latin American countries and as a result the producers agreed on an equitable division of the U.S. market. The U.S. government monitored this agreement. For the period that this plan was followed the value of coffee doubled, which greatly benefited coffee producers and the Latin American countries.
Brazil became the largest producer of coffee in the world by 1852 and it has held that status ever since. It dominated world production, exporting more coffee than the rest of the world combined, from 1850 to 1950. The period since 1950 saw the widening of the playing field due to the emergence of several other major producers, notably Colombia, Ivory Coast, Ethiopia, and, most recently, Vietnam, which overtook Colombia and became the second-largest producer in 1999 and reached 15% market share by 2011.
Recent additions to the coffee market are lattes, Frappuccinos and other sugary coffee drinks. This has caused coffee houses to be able to use cheaper coffee beans in their coffee.
Asia
During the cultivation, brewed coffee was reserved exclusively for the priesthood and the medical profession; doctors would use the brew for patients experiencing a need for better digestion, and priests used it to stay alert during their long nights of studying for the church.
India

Coffee came to India well before the East India company
Coffee's introduction to India is credited to the "Mughal era", particularly through a Sufi saint named "Baba Budan".
In the 17th century, the first record of coffee growing in India is following the introduction of coffee beans from Yemen, during his pilgrimage to Mecca. He planted these beans in the Chandragiri hills of Karnataka, which are now named Baba Budan Giri in his honor. This act marked the beginning of coffee cultivation in India, extending south to Kodagu.
In India, the word for coffee is "kaapi" in several South Indian languages, such as Tamil, Telugu, and Kannada.
Coffee production in India is dominated in the hill tracts of South Indian states, with the state of Karnataka accounting 53% followed by Kerala 28% and Tamil Nadu 11% of production of 8,200 Tonnes. Indian coffee is said to be the finest coffee grown in the shade rather than direct sunlight anywhere in the world. There are approximately 250,000 coffee growers in India; 98% of them are small growers. As of 2009, the production of coffee in India was only 4.5% of the total production in the world. Almost 80% of the country's coffee production is exported. Of that which is exported, 70% is bound for Germany, Russian federation, Spain, Belgium, Slovenia, United States, Japan, Greece, Netherlands and France, and Italy accounts for 29% of the exports. Most of the export is shipped through the Suez Canal.
Coffee is grown in three regions of India with Karnataka, Kerala and Tamil Nadu forming the traditional coffee growing region of South India, followed by the new areas developed in the non-traditional areas of Andhra Pradesh and Orissa in the eastern coast of the country and with a third region comprising the states of Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Tripura, Nagaland and Arunachal Pradesh of Northeastern India, popularly known as "Seven Sister States of India".
Indian coffee, grown mostly in southern India under monsoon rainfall conditions, is also termed as "Indian monsooned coffee". Its flavour is defined as: "The best Indian coffee reaches the flavour characteristics of Pacific coffees, but at its worst it is simply bland and uninspiring". The two well-known species of coffee grown are the Arabica and Robusta. The first variety that was introduced in the Baba Budan Giri hill ranges of Karnataka in the 17th century was marketed over the years under the brand names of Kent and S.795. Coffee is served in a distinctive drip-style "filter coffee" across Southern India.
Chikmagalur
Coffee is the cornerstone of Chikmagalur's economy. Chikmagalur is the birthplace of coffee in India, where the seed was first sown about 350 years ago. Coffee Board is the department located in Chikmagalur town that oversees the production and marketing of coffee cultivated in the district.
Coffee is cultivated in Chikmagalur district in an area of around 85,465 hectares with Arabica being the dominant variety grown in upper hills and Robusta being the major variety in the low-level hills. There are around 15,000 coffee growers in this district with 96% of them being small growers with holdings of less than or equal to 4 hectares. The average production is 55,000 MT: 35,000 MT of Arabica and 20,000 MT of Robusta.
The average productivity per hectare is 810 kg for Arabica and 1110 kg of Robusta, which are higher than the national average.
Arabica is a species of coffee that is also known as the "coffee shrub of Arabia", "mountain coffee" or "arabica coffee". Coffea arabica is believed to be the first species of coffee to be cultivated, being grown in southwest Arabia for well over 1,000 years. It is considered to produce better coffee than the other major commercially grown coffee species, Coffea canephora (Robusta). Arabica contains less caffeine than any other commercially cultivated species of coffee. Robusta is a species of coffee which has its origins in western Africa. It is grown mostly in Africa and Brazil, where it is often called Conillon. It is also grown in Southeast Asia where French colonists introduced it in the late 19th century. In recent years Vietnam, which only produces Robusta, has surpassed Brazil, India, and Indonesia to become the world's single largest exporter. Approximately one third of the coffee produced in the world is Robusta.
Japan
Coffee was introduced to Japan by the Dutch in the 17th century but remained a curiosity until the lifting of trade restrictions in 1858. The first European-style coffeehouse opened in Tokyo in 1888 and closed four years later. By the early 1930s there were over 30,000 coffeehouses across the country; availability in the wartime and immediate postwar period dropped to nearly zero, then rapidly increased as import barriers were removed. The introduction of freeze-dried instant coffee, canned coffee, and franchises such as Starbucks and Doutor Coffee in the late 20th century continued this trend, to the point that Japan is now one of the leading per capita coffee consumers in the world.
South Korea
Coffee's first notable Korean enthusiasts were 19th century emperors Sunjong and Gojong, who preferred to consume it after western-style banquets. After Korea's first coffee shop opened 1902, coffee was enjoyed by Korea's elites, who viewed coffee as a symbol of western culture and status. Coffee was later introduced to the general public in the 1950s by American soldiers stationed in Korea. The number of small, individually owned coffee shops, called dabang, increased rapidly; by the late 1950s, there were over 3,000 of them. In 1976, Korean beverage company Dongsuh Foods introduced the coffee mix, a mixture of instant coffee, creamer and sugar packaged in individual packets. This product contributed to the popularization of instant coffee, and later became an office staple after the Asian financial crisis. By the 1980s instant coffee and canned coffee had become fairly popular, with a more minor tradition of independently owned coffeehouses in larger cities. Toward the end of the century the growth of franchises such as Caffe Bene and Starbucks brought about a greater demand for European-style coffee, and led to the decline of dabangs.
Indonesia
Coffee was first introduced by the Dutch during colonization in the late 17th century. After several years coffee was planted on Indonesia Archipelago. Many coffee specialties are from the Indonesian Archipelago. The colloquial name for coffee, Java, comes from the time when most of Europe and America's coffee was grown in Java. Today Indonesia is one of the largest coffee producers in the world, mainly for export. However, coffee is enjoyed in various ways around the archipelago, for example, the traditional "kopi tubruk".
Philippines
The Philippines is one of the few countries that produces the four varieties of commercially viable coffee: Arabica, Liberica (Barako), Excelsa and Robusta. Although it is generally said that coffee was introduced to Lipa in 1740 by a Spanish Franciscan friar, there is actually little first-hand evidence to substantiate this. Regardless, by the early 19th century, coffee was being cultivated throughout the Philippines and subsequently exported to America and Australia, followed by Europe with the opening of the Suez Canal. Lipa is commonly attributed as being the center of this cultivation, until roughly 1889, when its industry abruptly failed, likely due to pests, coffee rust (which the Philippines had managed to avoid for longer than the rest of the world), and political factors.
Following this destruction, the Philippines' place in the global coffee supply chain faltered, and would be slow to recover. Throughout the 20th century, various government initiatives were implemented to revive the industry, despite that the Philippines would gradually begin importing more instant coffee than it was exporting. Regardless, a coffee culture has been developing since the 1990s, following the Philippines joining the International Coffee Organization in 1980, and now many specialty coffee shops can be found around the country.
Vietnam
Vietnam is one of the world's main coffee exporters. Arabica is the first imported coffee variety to Vietnam since 1857. Initially being grown in the northern provinces, the cultivation of coffee spread until it reached the Central and Western Highlands, which now produce a majority of Vietnam's coffee. Most notably among these is the city of Buôn Ma Thuột, which is known as the "coffee capital of Vietnam".
Trung Nguyen Coffee was founded in 1996 by Dang Le Nguyen Vu, and is the premier coffee brand in Vietnam to this day.
Production
The first step in Europeans' wresting the means of production was effected by Nicolaes Witsen, the enterprising burgomaster of Amsterdam and member of the governing board of the Dutch East India Company who urged Joan van Hoorn, the Dutch governor at Batavia that some coffee plants be obtained at the export port of Mocha in Yemen, the source of Europe's supply, and established in the Dutch East Indies; the project of raising many plants from the seeds of the first shipment met with such success that the Dutch East India Company was able to supply Europe's demand with "Java coffee" by 1719. Encouraged by their success, they soon had coffee plantations in Ceylon, Sumatra and other Sunda islands. Coffee trees were soon grown under glass at the Hortus Botanicus of Leiden, whence slips were generously extended to other botanical gardens. Dutch representatives at the negotiations that led to the Treaty of Utrecht presented their French counterparts with a coffee plant, which was grown on at the Jardin du Roi, predecessor of the Jardin des Plantes, in Paris.
The introduction of coffee to the Americas was effected by Captain Gabriel des Clieux, who obtained cuttings from the reluctant botanist Antoine de Jussieu, who was loath to disfigure the king's coffee tree. Clieux, when water rations dwindled during a difficult voyage, shared his portion with his precious plants and protected them from a Dutchman, perhaps an agent of the Provinces jealous of the Batavian trade. Clieux nurtured the plants on his arrival in the West Indies, and established them in Guadeloupe and Saint-Domingue in addition to Martinique, where a blight had struck the cacao plantations, which were replaced by coffee plantations in a space of three years, is attributed to France through its colonization of many parts of the continent starting with the Martinique and the colonies of the West Indies where the first French coffee plantations were founded.
The first coffee plantation in Brazil occurred in 1727 when Lt. Col. Francisco de Melo Palheta smuggled seeds, still essentially from the germ plasm originally taken from Yemen to Batavia, from French Guiana. By the 1800s, Brazil's harvests would turn coffee from an elite indulgence to a drink for the masses. Brazil, which like most other countries cultivates coffee as a commercial commodity, relied heavily on slave labor from Africa for the viability of the plantations until the abolition of slavery in 1888. The success of coffee in 17th-century Europe was paralleled with the spread of the habit of tobacco smoking all over the continent during the course of the Thirty Years' War (1618–1648).
For many decades in the 19th and early 20th centuries, Brazil was the biggest producer of coffee and a virtual monopolist in the trade. However, a policy of maintaining high prices soon opened opportunities to other nations, such as Venezuela, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Indonesia and Vietnam, now second only to Brazil as the major coffee producer in the world. Large-scale production in Vietnam began following normalization of trade relations with the US in 1995. Nearly all of the coffee grown there is Robusta.
Despite the origins of coffee cultivation in Ethiopia, that country produced only a small amount for export until the twentieth century, and much of that not from the south of the country but from the environs of Harar in the northeast. The Kingdom of Kaffa, home of the plant, was estimated to produce between 50,000 and 60,000 kilograms of coffee beans in the 1880s. Commercial production effectively began in 1907 with the founding of the inland port of Gambela. 100,000 kilograms of coffee was exported from Gambela in 1908, while in 1927–1928 over 4 million kilograms passed through that port. Coffee plantations were also developed in Arsi Province at the same time and were eventually exported by means of the Addis Ababa – Djibouti Railway. While only 245,000 kilograms were freighted by the Railway, this amount jumped to 2,240,000 kilograms by 1922, surpassed exports of "Harari" coffee by 1925, and reached 9,260,000 kilograms in 1936.
Australia is a minor coffee producer, with little product for export, but its coffee history goes back to 1880 when the first of 500 acres (2.0 km2) began to be developed in an area between northern New South Wales and Cooktown. Today there are several producers of Arabica coffee in Australia that use a mechanical harvesting system invented in 1981.
関連項目
外部リンク
- A History of the World in 6 Glasses, by Tom Standage: a review by blaqswans.org
- Dorothee Wierling: Coffee during the World War I, in: 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War.
| この記事は、クリエイティブ・コモンズ・表示・継承ライセンス3.0のもとで公表されたウィキペディアの項目History of coffee(28 May 2025, at 19:29編集記事参照)を翻訳して二次利用しています。 |
